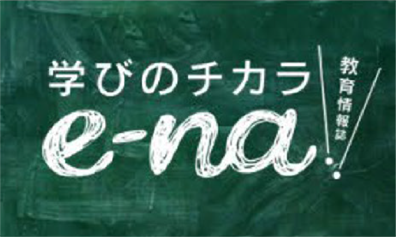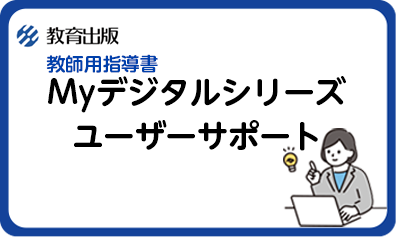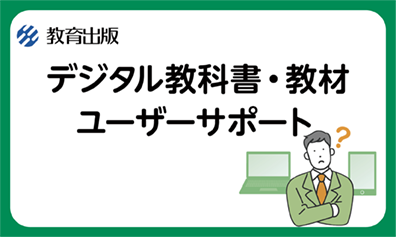数学問はず語り 第4回
『円』の世界,『楕円』の世界(その2)
岡本光司(元静岡大学教授)
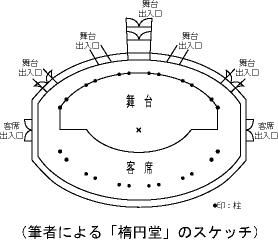
楕円堂
静岡市と清水市にまたがり富士山と駿河湾を望む景勝地「日本平」に,静岡側から向かう有料道路を車で2,3分走ると,なだらかな丘陵に広がる舞台芸術公園に着く。そこには二つの劇場がある。一つは野外劇場「有度」で,敷地内の最も緑が深い谷に向かって配置されている。これもすばらしい劇場であるが,さらに,京都の嵯峨野を想わせる竹薮の中の小道を抜け,茶畑を左右に,晴れていれば富士を望みながら数分歩くと,そこに私がぞっこん惚れ込んでいる小劇場「楕円堂」が見えてくる。言うまでもなく,「楕円堂」はフロアー全体が楕円形をしていて,そのフロアーを操作することにより,一部を客席にすることができるようになっている。しかも,その舞台部分が楕円の2定点と長軸と短軸が交わる点を含むように前に迫り出しているので,舞台のほうが客席部分より広くなる。座席数はわずか100である。何とも贅沢な劇場なのである。
この「楕円堂」は,磯崎新氏と静岡県舞台芸術センターの芸術総監督鈴木忠志氏の構想と設計によるものであるが,そこには,劇場は単に演劇を行う場所ではなく劇場そのものが演劇を構成する重要なファクターであると考える鈴木氏の劇場観がみごとに生かされている。
過日,その鈴木氏にお会いした折り,常々私が「楕円堂」について知りたいと思っていたことを直接うかがうことができた。それは,なぜ「楕円」堂なのかということであった。
鈴木氏は,その理由を二つあげられた。一つは,16世紀末,イタリアのヴィチェンツァに建てられたルネッサンス期の有名な劇場「テアトロ・オリンピコ」を模した劇場を現代日本に造りたかったということであった。その劇場は,舞台への出入口が奥に3つ,左右に2つ,計5つある。また,舞台は矩形であるが,観客席は半円形ではなく楕円を半分にした形になっている。これは,地形の制約によるものと考えられているが,鈴木氏は,この特徴を取り入れ,舞台への出入口が5つあり,しかも全体が楕円形になる劇場を意図して構想,設計されたという。
「楕円堂」の楕円形は,長軸が9間(約16.4m),短軸が6間(約10.9m)で,x2/8.22+y2/5.52=1と表せるもので,焦点はおよそ(6.1,0),(-6.1,0)になる。また,両軸の交点,すなわち中心点の真上に天窓がつけられている。
そうした舞台建築としての構想を実現されたことへの感動もさることながら,さらに私にとって興味深かったのは,もう一つの理由として鈴木氏が語られた楕円形の中に収まっている舞台と役者との関係についてである。
役者には舞台の「中心」に自分を置きたいという潜在的な志向があるのだという。日本の歌舞伎においても,当初,舞台の「中心」で演技ができたのは座主であり,座頭であった。やがて,その座は最も芸に秀でた役者が位置するようになったという。これは象徴的な事柄であるが,過去も,現在も,役者は目を閉じていてもわかるように舞台空間を自分の中に取り入れ,「中心」とそこからの距離を意識して演技しており,円形であれ,矩形であれ,舞台の「中心」は大変重要な機能をはたしているのだという。
ところが,舞台が楕円形になると,役者は,その舞台空間をたやすく自分の中に組み入れることができなくなり,「中心」やそこから周りまでの距離を身体で感じ取ることが容易ではなくなるという。そこに役者の迷いが生じ,その迷いが役者に舞台空間との新たな戦いを求め,その結果,演技に深みがみられるようになるのだという。
鈴木氏は,そうした今までにない舞台での演出を手掛け,幾つものみごとな演劇を創ってこられた。「この舞台を使いこなすことができるのは,私だけでしょうね」と最後に言われた鈴木氏の言葉は印象深いものであった。
1定点を中心とし,そこから等距離にある「円」の世界は,役者さん達ばかりでなく,私達にとっても,捉えやすく,行動しやすく,安心できる世界である。しかし,それがひと度,2定点とそこからの距離の和が一定な軌跡の中に立たされると,人は戸惑い,自分を含む空間を自分の中で構築し直さなければならなくなるのだろう。しかも,それは,決して容易なことではなさそうである。
「円」は「楕円」の式(x2/a2+y2/b2=1)においてa=bになった特殊な形(x2/a2+y2/a2=1,x2+y2=a2)である。その特殊な世界「円」から「楕円」の世界に入っていくということは,私達にとっても,しんどいことではあるが,結構面白いことなのかもしれない。そこでは,「円」の世界では扱えなかった複雑で微妙な人間模様さえ描くことができるのではないか,そんな予感さえしてくるのである。