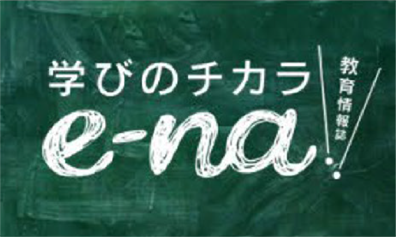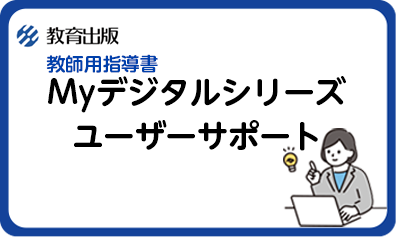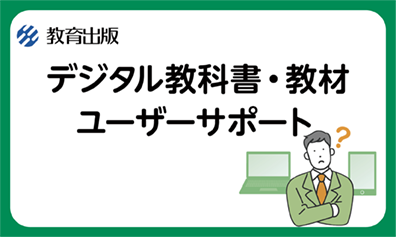数学問はず語り 第5回
『円』の世界,『楕円』の世界(その3)
岡本光司(元静岡大学教授)
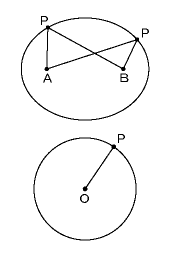
楕円
生涯一人の人を想い続け,ただ一つの愛を貫き通す人もいる。それを一方の極とするならば,他方の極に,尽きることなく異性を求め続けてやまない多情多感な人もいる。愛のあり様は人それぞれであり,その善悪,是非を論じても意味のないことであるが,視点を変えて,そこに潜む愛へのエネルギーの違いといったものを人間模様の一つとしてとらえてみたらどうだろう。
三浦朱門氏の小説の中に『楕円』という題名の小説がある。その小説のモチーフはそうした視点から,一人の男の愛の軌跡を描こうとしたものである。一人の平凡な男性が,二人の女性を愛し,ある時は一方の女性に心が傾斜し,また,ある時は他方の女性に強く心を奪われていく。そうした男と二人の女のあり様が巧みに描かれた小説である。
私は,ある時期,数学の文脈を離れて使われていく数学用語に関心をもち,その事例を収集していた。そこには,小説の題名として使われた数学用語もあった。三浦氏の小説もその一つである。氏は,この『楕円』以外にも『正四面体』,『双曲線』といった題名の小説を書いておられる。
私は,このことに興味をもった。なぜ数学用語としての『楕円』を使われたのか,小説を書いているどの時点で『楕円』を使おうと思われたのか,などなど,臆面もなく三浦氏にお尋ねしたことがある。それに対して,氏からかなり長文の返信をちょうだいした。その中で,氏は『楕円』という題名をつけた動機について,以下のように述べられていた。
「二人の女の間をゆれ動く男の心。彼の心はある時は一方に重く,別の時は他の方に重い,しかし,愛を求めようとする心の総エネルギーは変わらないかもしれない。そんな時に,「二点間の距離の和が一定である点の軌跡」ということで「楕円」などという題をつけたのです。」
このことを,あえて楕円という図形の上で表してみると,2定点A,Bが女性A,女性Bで,曲線上を回る男性,点Pが,ある時は点Aに近づき,またある時は点Bに近づいていく。が,A,BとPとを結ぶ線分の長さの和(愛の総エネルギー)は一定であるということになる。
この図からは男の哀れさのようなものが見え隠れしているようにも思える。一人の女性をのみ愛し通す愛のあり様は,1定点のまわりを一定距離で回る『円』ということになるのだろう。いずれにしても男は動点なのだろうか。そう言ってしまっては,お叱りを受けるかもしれないが。
愛のあり様に限らず,さまざまなものと対峙するとき,あなたは『円』の世界に生きるか,生きたいと願うか。『楕円』の世界に生きるか,生きたいと願うか。否,もっと危うく複雑な世界を求めるか。「それが,問題だ」ということにして,「円と楕円の世界」の連載を終わらせていただく。