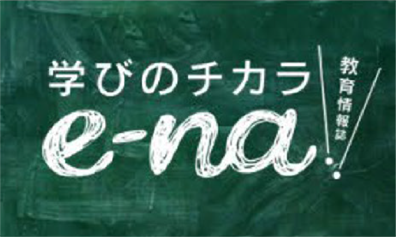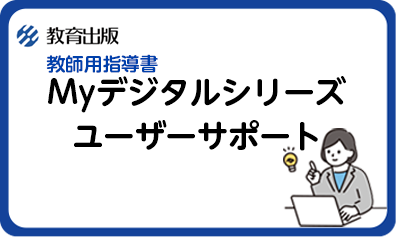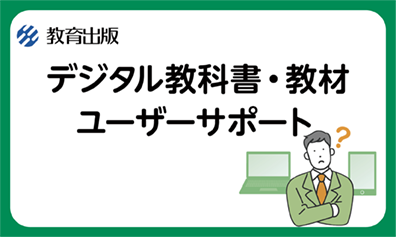数学問はず語り 第7回
点描/モンゴルの人々,そして算数・数学教育(その2)
岡本光司(元静岡大学教授)

写真1
首都ウランバートルの中心から車で15分か20分走ると,そこはもう草原である。初めてモンゴルへ行った年,私はリャンホァさんと彼女のお兄さんに案内されて,車でウランバートルから70kmほどのところにある草原の中の保養地テレルジに行った。その日は,明日から新年度の授業が始まるという8月31日であった。
途中,放牧の馬や羊を追う何組かの子ども達に出会った(写真)。私の目には,彼等の姿は生き生きとし,何とも逞しく映った。彼等も明日から学校である。遊牧民の子ども達は,移動しながらそれぞれの地域の寄宿制の学校に行くのだとリャンホァさんから聞いていた。私はそうした彼等とことばを交わしてみたくなり車を止めてもらった。
「明日から学校へ行くんだね?」と声をかけると,一人の子どもはうなずいたが,もう一人の子どもは明日も馬を追う仕事をするのだと言った。その子どものことばを聞いたリャンホァさんは,新年度を迎えても学校へ行かない子どももいるんですよと顔を曇らせた。詳しい事情はわからないが,それはモンゴルにとって大きな問題なのだろう。ただ,はっきりしていることは,日本の子どもの不登校とはまったく意味が違うことである。彼等は,家族の一員として重要な役割をはたしながら,そこで生きる知恵を学んでいる。馬を追う草原が本物の「学び」の場になっている。
そんなことを考える私の脳裏を「生きる力」ということばがよぎった。そして,近年の日本の子ども達は「生きる力」が萎えてきている,日本の教育では子ども達に「生きる力」をつけようと躍起になっているのですよ,などと彼等に言ったらどんな顔をするだろうか,まったく理解できないだろうなと思ったりした。彼等は,今そこで逞しく生きている,生活している。そうした子ども達に「生きる力」などということを取り立てて言う必要はないし,意味もない。一方,日本の子ども達は「生活する」ためには「生きる力」が必要であり,大切なのだといわれている。奉仕の精神を身に付けるためにボランティアをしなさい,苦労をしなさいとも言われている。
いずれの国の子ども達も,時代と国を選んで生まれてきたわけではないし,それぞれが今そこにある現実と対峙しているという意味では共通なのだが,この両極に位置するような二つの国の子ども達を思うと,改めて「生きる」ということの意味について考えさせられる。
モンゴルでの客人への最高のもてなしは,羊や山羊のバーベキューである。私はその過程の一部始終を見ることができた。ただ,目の前の可愛い山羊が一瞬の内に締められ,皮を剥ぎ取られていく様子は恐くて凝視することができなかった。もっとも,ろうそくで光をとったゲルの中で,その肉や内蔵を口にほおばったときには,その美味に残虐とも思える光景を忘れてしまっていたが。
そうした初体験も忘れ得ないことではあるが,私にとって興味深かったのは食後の談笑の中で山羊を締めた青年から聞いた話であった。「モンゴルの男達は,羊や山羊を締め,皮を剥ぎ,内蔵をえぐり出し,料理ができて初めて大人の仲間入りが認められるのだ」と。「それは成人になることへの一つの関門なのだ」と。彼は,形式としての式ではなく,生きていくために一人前になるということはどういうことなのかを語ってくれた。そこには「巣立つ」ということの真の姿があるような気がした。
日本だけのことではないのかもしれないが,特に日本では,今や「成人」という言葉は死語に近い。二十歳という成人と非成人とを分ける法律にすら違和感が感じられる。大人になりきれない成人がおり,騒がしくて式にならない成人式があり,子ども達に信念をもって「大人への関門」を突きつけることができなくなっている大人達がいる。現代日本においては,「大人になることへの関門」といったものが必要なのかどうか。それはもはや意味をもたないものなのか。「失ってしまったもの」なのか,「否定してきたもの」なのか。
彼の話は,そんな日本という国を改めて考えさせてくれた。
ウランバートルの町を歩いていると自分が日本人であることを忘れてしまうことがある。そこにいることに何の違和感も感じずにいられる。草原へ出ると故郷の暖かい空気に包まれているような気分になる。零下何十度という厳寒の時は別として,草原のゲルで遊牧の人達と交わった日本人は口を揃えてモンゴルのすばらしさを語り,著名な方々の文章や映像が,その想いを増幅させてくれている。
そこにあるものは何なのか。モンゴル人は遊牧民であり,今なお,基本的にはその流れの中にいる。一方,日本人はもともとは農耕民族でありながら,ハイテク産業やサービス業を中心とした国を創り上げてきた民族である。これほどに異なる民族でありながら,なぜ多くの日本人がモンゴルにあこがれ,共鳴するのだろうか。
私には学問的な考察はできないので,直感でしかないが,それはモンゴル人と日本人の「精神」や「感性」に潜む共通性ではないか。そう思えてならない。「細やかな心遣い」,「師への礼」,「地に根ざした生活」,「大人になることへの関門」といったことを無いものねだりのように語った私の中には,そうしたものの中に潜む機微や心根を感じ取れる感性があり,それらを「善きもの」と感じてしまう精神構造のようなものがあるのではないか。これは,欧米の人達がモンゴルから感じ取るものとは異なるものだと思う。
そんな私が郷愁のような想いでモンゴルの人々との「できごと」を点描してきた。それはそれでよいとして,「で,あなたはどうすればよいと言うのか」と問われると私は頭を抱えてしまう。モンゴルには日本が失ってしまった「もの」や「こと」が残っている,モンゴルには日本の「ふるさと」があると言ったところでしかたがない。また,単なる復古精神で解決できるようなことでもない。
そうした「問い」をめぐって,今,私の頭の中には,ぼおーとしたイメージがあることはある。唐突ではあるが,私の好きな演劇にかかわらせて比喩的に言わせてもらうならば,それはこんなことである。
世界の前衛演劇をリードした巨匠ハイナー・ミュラーは,前衛演劇と伝統的なテキスト重視の演劇との間の亀裂を修復し,止揚するために古代ギリシャ悲劇に着想を得たといわれている。静岡県舞台芸術センターの芸術総監督鈴木忠志は,日本の古典的な能や歌舞伎の技と心を取り入れることによって世界に通じるすばらしい演劇を創出し続けている。前者にあるのは前衛と伝統との間に「回帰すべき原点」を持とうとしたことである。後者にあるのはグローバル化が進む現代においてなお,固有の文化を重視し,それを生かすことによって新たなるものを創造しているということである。
次なる時代に向かって,何を考え,何をなすべきか。そのための視点を,この二つの演劇活動は物語っているのではないかと思うのである。