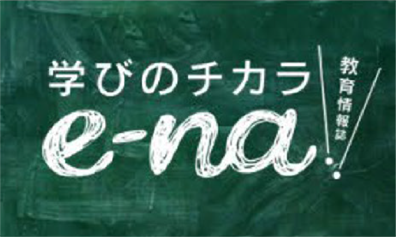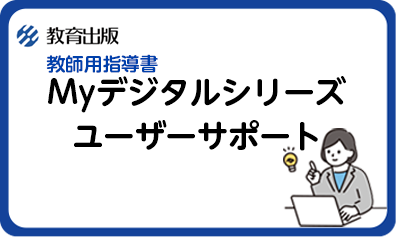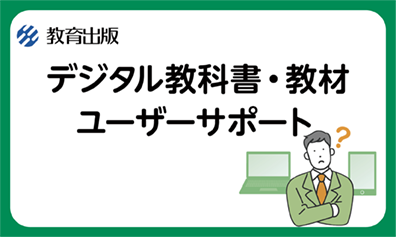数学問はず語り 第8回
点描/モンゴルの人々,そして算数・数学教育(その3)
岡本光司(元静岡大学教授)
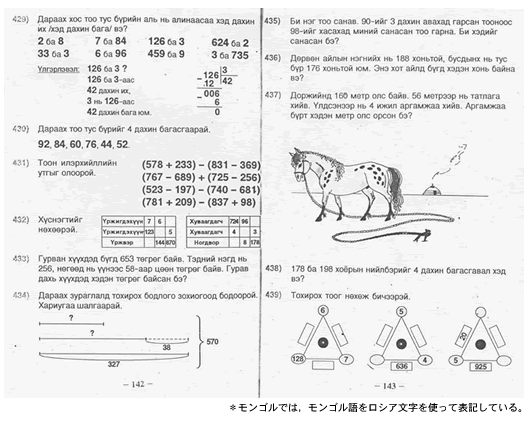
イメージ1
◆三度のモンゴル訪問の中で,私は,その都度ウランバートルの小学校,中学校,高校の算数・数学の授業を参観してきた。欧米の国々の算数・数学教育に関する情報は数多くあるが,モンゴルのそれに接する機会は無に等しかっただけに,授業の実際や算数・数学の内容,さらにはその背景にある数学教育についての考え方に触れて,驚くこともあったし,あれこれ考えさせられることもあった。
今回は,モンゴルの学校における算数・数学の内容の実際を一部ではあるが,そのまま紹介してみることにする。
まず,教科書を見ていただこう。これは小学校2年(モンゴルの小学校は4年間なので,日本の4年生にあたる)の算数の教科書である(下にその翻訳の一部)。日本の教科書とは異なり,全て問題形式で記述され,この教科書にはこうした問題が全部で501題載せられている。
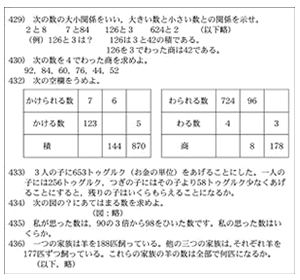
イメージ2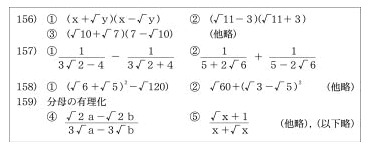
イメージ3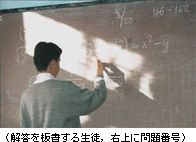
イメージ4
◆この教科書は,形式としては日本の昭和初期の緑表紙教科書に似ている。また,内容的には,「かけ算」の単元では「かけ算」だけ,「わり算」の単元では「わり算」だけといったようにブロック形式で教材配列がなされている現行の日本の教科書に比べ,「かけ算」と「わり算」を並行して扱い,同時に既習の「たし算」,「ひき算」も含めた四則混合算や「かっこ」を使った計算も扱っているところに特徴がある。
算数の授業では,こうした問題を次々に解かせていく。1校時(40~45分)に扱う数は5,6題である。
次に中学校(3年間)の数学の内容を見てみよう。
私が参観した中学3年の数学の授業では,その時間(50分),上掲のものと同じような教科書の156番から162番の問題が扱われていた。
その問題は,次のようなものである。(イメージ3)
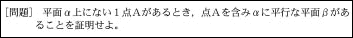
イメージ5
日本の中学3年の内容に比べて大変高度なものである。
高校の数学の内容には,さらに驚かされた。教科書は旧ソ連の教科書の翻訳本で,そこに載っている次のような証明問題が扱われていた。(イメージ5)
◆授業は,こうした証明問題を生徒が考え,その解答を教師が黒板いっぱいに板書し,それを生徒が黙々とノートに書き写 すというものであった。
算数・数学の学習内容の紹介だけに終わってしまったが,率直な感想は,扱われている内容の数学的レベルの高さである。日本では,平成14年度から学習指導要領の最低基準をさらに下げてしまった。モンゴルの算数・数学の内容と比べるとき,少なくとも,そのレベルに関しては落日の思いを禁じ得ない。

イメージ6
モンゴルと日本の算数・数学教育の違いは,こうした内容だけではない。さらに大きく異なるのは,授業展開の方法であり,算数・数学教育ということの位 置付け,価値付けである。次回は,そうしたことを紹介し,算数・数学教育のあり方について考えてみようと思う。