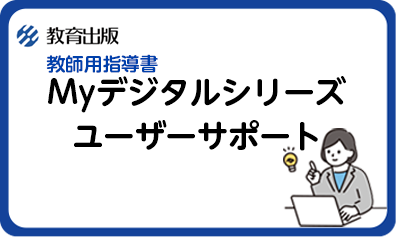数学問はず語り 第10回
算数・数学教育への「こころざし」(その1)
岡本光司(元静岡大学教授)
◆私は「こころざし」という言葉が好きである。大望とは違う,もちろん野望ではない。大望や野望は極めて私的な望みであったり,ぎらぎらした心の露出であったり,策を労してはばからなかったりする。それに対して,「こころざし」にあるものは,内に秘めた熱さであり,厳しさの中にあってなお立ち向かおうとする果敢さであり,真と信じるものを追い求めてやまない心意気である。どこかに哀愁を漂わせるロマンすら感じられる。
こうした「こころざし」という視点で,算数・数学教育をみてみると,どんなことが思い浮かぶだろうか。
私の場合,どんな時代のどんなことに日本の算数・数学教育への「こころざし」を感じるかというと,それには2つのタイプがある。
一つは政治体制や社会体制に大変革が起こり混乱の中で新たな創造が始まったり,それらが一気に崩壊して無に等しい状況からの復興に向けた営みが始まる時にみられる「こころざし」である。開国を機に長い和算の伝統を切り捨てて洋算を取り入れた明治時代初・中期と,戦後の復興の中で生活単元学習に取り組んでいった昭和20年代後半の算数・数学教育にみられた「こころざし」がその例である。
もう一つは社会の変化や学問,科学技術等の進展に伴って,それまでの算数・数学教育に行き詰まりが生じたり,そのあり方や内容に大きな変革が求められるようになった時にみられた「こころざし」である。20世紀初頭,欧米を中心に湧き起こった数学教育改良運動の影響を強く受けた大正から昭和初期と,本稿では触れないが数学教育の「現代化」を標榜して格闘した昭和40年代の算数・数学教育にみられた「こころざし」がその例である。
私は数学教育史の専門家ではないので,これらの各時代の算数・数学教育の全貌をとらえ詳細に歴史的な考察を加えていくことはできない。私にできることといえば,きわめて「私的」な切り口から,その一面をとらえてみることぐらいである。それをお許しいただいた上で,以下,私が感じた算数・数学教育への「こころざし」について綴っていくことにする。
◆私の手元に二つの古い文献がある。一つは明治14年12月に発行された『東京數學會社雜誌第四拾貳號附録』であり,一つは明治22年に著された藤澤利喜太郎編纂による『數學用語英和對譯字書』である。いずれも明治時代,洋算の導入に合わせて必要となった数学用語としての英語の翻訳にかかわる文献である。前者は明治13年8月に発足した東京數學會社主催の訳語会の記録であり,後者は藤澤利喜太郎氏が私案としての訳語をまとめたものである。
前者,訳語会の記録には,柳楢悦を議長,中川將行を草按者に総勢27人の学者が数回にわたって一堂に会し,中川が提示した一つ一つの英語の数学用語の和訳原案をめぐって交わした議論が詳しく記載されている。例えば,「product」の訳語の原案として出された「得數または積」に対しては,委員の中から「相乗積,乗積,相乗數,乗果」といった対案も出され,その各々の適否が議論され,最後に,議長の裁量で,賛同者が多いことをもって「積」とすることに決められていく過程が記録されている。和算から洋算への移行の中で展開された「出来事」の一コマではあるが,この会議録に,何かが生み出されていく時の生々しさが感じられ,感動を覚えるのである。
以下にその部分のみ掲載してみる。
product,得數又積
十五番(荒川)曰「得數」ヲ除キテ單ニ積ノミニ定ムヘシ
三番(岡本)曰「得數」ヲ削リ「積」ニ定ムルハ可ナリ然レドモ唯タ「積」ノミニテハ不十分ニ思ハル故ニ「相乘積」トスヘシ
議長曰「積」ハ坪ト云フ意ノ字ニテ是迄ノ習ヒハ形アルモノヲ云ヒ形アルモノノ外ハ積ノ字ヲ用ヒス是ハ數アリテ形ナシ熟考アリタシ
十五番曰「積」ハ二乘三乘其餘何乘ニテモ可ナリト考フ且ツ必ス平面或ハ立方積ニモ限ラサルヘシ積ハ物ヲ積ムノ意ナレハ何乘ニテモ差支ナシ
十七番(平岡)曰相乘セシモノハ従來「積」ト云ウ併シ「乘積」トスル方カ可ナルヘシ
十五番曰十七番ノ説ノ如クナレハ乘シタル積或ハ和シタル積ナドト云フ如クナリテ不可ナリ
六番(駒野)曰十五番ニ同意ス
四番(肝付)曰「プロダクト」ノ意味ニ最モヨク適當スヘキハ乘果ト譯スヘシ
十一番(磯野)曰「プロダクト」ハ相乘セシ數ナリ故ニ「相乘數」ト改メン
三番曰「相乘積」トスヘシトノ説ヲ述ヘシカ今マタ十一番ヨリ「相乘數」ニナスヘシトノ説出テタルヲ以テ考フルニ積ノ字ハ少シク穏當ナラスト思ハル「プロダクト」ハ單ニ相乘シタルモノト見テ可ナリ由テ更メテ「相乘數」ニ同意ス
十番(川北)曰相乘數トスルヲ賛成ス
草按者曰加ヘタル者ハ和,割テ出タルモノハ商,減シテ残リタルモノハ差ト各草純ノ名稱アリ然シテ唯タ乘シテ得タル數ノミニ單一ナル名稱ナシト云フ説ハ不思議ノコト考フ依テ乘セシモノニハ「積」トイフ單一ノ名アリト信セシヲ以テ此譯ヲ下シタリ坪ノ意ニ用ルニハ面積或ハ立体積トスレハ差支ナシ
十八番(眞山)曰十五番ニ同意
議長説ノ盡キタルヲ見テ,先ツ原按通ニ同意ノ者ヲ起立セシムルニ少數ナリ次ニ「得數」ヲ削リ「相乘數」「乘積」及ヒ「乘果」ト修正スルノ同意ヲ表セシムルニ各少數ニテ「積」トスルニ可トイフ者多數ナリ依テ「積」ニ決定シタリ
◆また,後者の文献からは,さらに興味深い文言を見出すことができる。藤澤利喜太郎氏といえば明治時代の数学教育に多大な功績を残した著名な数学者であるが,その藤澤氏が『數學用語英和對譯字書』の前書きの文末を次のような言葉で結んでいる。
「最後ニ余ハ本書ニ載セタル訳語ニ付キ異見或ハ別ニ新案ヲ持スル人ニ向ツテ東京
小石川諏訪町三十六番地藤澤利喜太郎宛教示垂レランコトヲ請願スルモノナリ。」
藤澤氏の自信の現れと受け取ることもできるが,当時の数学教育界の重鎮が,あえて自らの訳語に対して異見も受け入れますよと,開かれた議論を求めていることに私はわくわくしてしまうのである。この著書が著された明治22年といえば,大日本帝国憲法発布の年である。「万機公論に決すべし」といった精神の基に議論沸騰,提案勃興した時代の先人の英知をここから垣間見ることができる。
この二つの文献は,日本が近代国家としての基礎固めを進めていった激動の時代にあって,数学や数学教育の世界における新たなものの胎動に向けた熱き息吹の一端を私に感じさせてくれるのである。白紙の上に文字を書き込んでいこうとするときのような緊張感と真剣さ,我々こそが成さねばならないのだといった自負と高揚,そんなものが算数・数学教育への「こころざし」として伝わってくる。しかも,そこには何とも言えない人間味すら見え隠れしているのである。