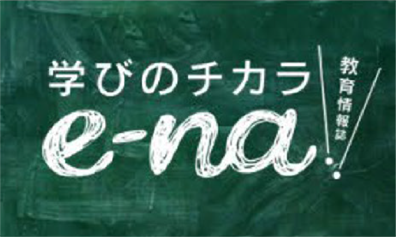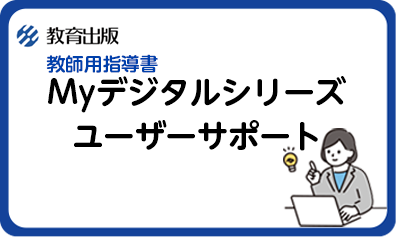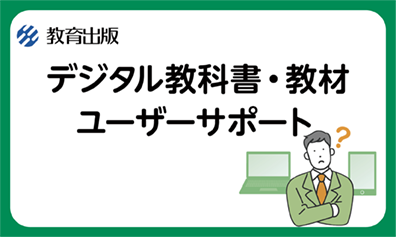数学問はず語り 第11回
算数・数学教育への「こころざし」(その2)
岡本光司(元静岡大学教授)
算数科の一般目標
(1) 算数を,学校内外の社会生活において,有効に用いるのに役だつ,豊かな経験を持たせるとともに,物事を,数量関係から見て,考察処理する能力を伸ばし,算数を用いて,めいめいの思考や行為を改善し続けてやまない傾向を伸ばす。
(a) 一般社会人の生活,特に経済生活をしていくのに必要な数的資料として,どんな種類のものがあるか,また,これをどこから手にいれることができるかなどの知識を広めるとともに,その資料を利用する能力や傾向を伸ばす。
(b) 日常生活を,数量関係から見て分析したり,総合したりして,筋道をたて,問題をとらえる能力を伸ばすとともに,これを解決する能力を伸ばす。
(以下,略)
数学科の一般目標
1.数学の有用性と美しさを知って,真理を愛し,これを求めていく態度を養う。
2.明るく正しい生活をするために,数学の果たしている役割の大きいことを知り,正義に基づいて自分の行為を律していく態度を養う。
3.労力や時間などを節約したり活用したりする上で,数学が果たしている役割の大きいことを知り,これを勤労に生かしていく態度を養う。
4.自主的に考えたり行ったりする上に,数学が果たしている役割の大きいことを知り,数学を用いて自主的に考えたり行ったりする態度を養う。
(以下,略)
◆まるで青年が書いたような文である。書生ぽい文である。今読むと,よくもまあ,臆面もなくここまで書けたものだと思うが,焦土と化した祖国の復興に向けて,算数・数学教育に託したいことが生き生きと書かれている。算数・数学教育の目標が単に算数・数学の理解という範囲を越えて,時代が要請する人間教育を目指したものになっている。味もそっけもないお役所的な文言を連ねた現在の学習指導要領と比べてみると雲泥の差がある。
これを皆さんは,どう読むだろうか。私は,この時代にあって,この時代だからこそ掲げることのできた算数・数学教育への「こころざし」と読む。ここには,「生きる力」に象徴されるような失ってしまったものの回復に対処していかざるを得ない現在の教育とは正反対のプラス志向がある。もはや失うものとてない貧しく混沌とした世にあって,次の時代を担う子ども達に託したい切なる願いが鮮明に描かれている。執筆にかかわった方々が高く掲げた「こころざし」がひしひしと伝わってくる。それに私は打たれる。