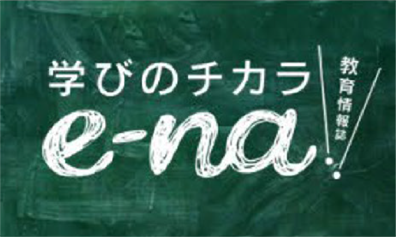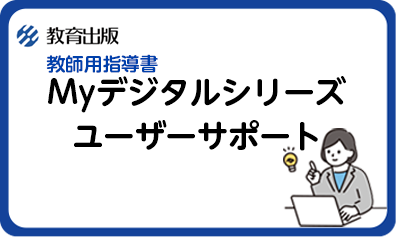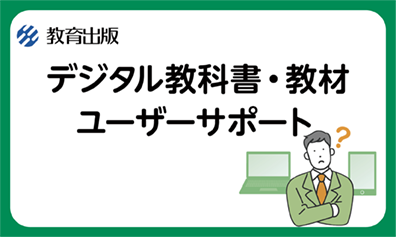数学問はず語り 第12回
算数・数学教育への「こころざし」(その3)
岡本光司(元静岡大学教授)
◆昨年度前期,私は静岡大学教育学部附属静岡中学校で非常勤講師として毎週1回,2時間続きの選択数学を担当させていただいた。そこで私がやったことは,数学を選択した3年生10人とユークリッドの『原論』を読むことであった。中学2年で図形の論証を学び始めた彼らに,そこでの論証と『原論』での論証のどこがどう違うかを検証しながら,数学の香りに触れてもらおうとした。今思うと,それは無謀な企てであった。生徒諸君には,申し訳ないことをしてしまったと思っている。
そんな授業をしながら,その間ずっと私の脳裏をかすめ続けていたことは,数学といえば『原論』を読むことであったといわれるヨーロッパの国々での数学教育のことであった。ラテン語とともに形式陶冶という観点から『原論』を読まされていた当時の学生達のことであった。私の生徒達は,授業の後半,ユークリッドの第五公準に目を向け,非ユークリッド幾何学の誕生へと関心を移していってくれたので救われたが,この授業は,19世紀末,『原論』による数学教育が限界に達していたであろうことを実感させてくれる機会にもなった。
1901年,グラスコーで開かれた英国学術協会の席上で行われたジョン・ペリーの講演は,そうした『原論』を中心とする数学教育の状況を打破していくための先鞭をつけるものであったと言われている。それは欧米における数学教育改良運動の始まりであった。
この数学教育改良運動は,社会の変化に対応し,新たな数学教育の世界を切り開いていったという意味で,それ自身を算数・数学教育への「こころざし」といってよいのだが,その詳細については専門の著書,論文等に譲ることにする。ここでは,上述のペリーの講演に目を向けてみたい。その中で特に私が魅せられたのは「数学学習の有用さ」について語られている部分である。その一部を抜粋してみる。
・知力の発達においても,単なる数学の学習においても,高尚な情緒をつくり,知的喜びを与える。
・人々がその生涯を通じて,自分自身を教育し続け,精神と知力とを発達させることができるようにし,そしてこの目的のために,彼らのすべての経験を利用できるようにする。
・一人の人間に,自分のため以外のことがらを考える重要性を教え,それによって,現在の権力の恐ろしい支配から自分自身を解放し,他人に服従していると他人を支配しているとにかかわらず,彼が最高の存在の一人であることを確信させる。
(ペリー,クライン著丸山哲郎訳『数学教育改革論』明治図書1974)
この文には1世紀前に語られたものとは思えない新鮮さがある。時代的な制約を受けてはいるものの,いまなお,そこには数学的精神の何たるかを私達に指し示してくれるものがある。これは数学教育改良運動を支えた思想の一端であるかもしれないが,私はここに,古きものから脱皮し,新たな創造に向かわんとする算数・数学教育への「こころざし」を感じるのである。この運動は大正から昭和初期にかけて日本の算数・数学教育にも大きな影響を及ぼし,当時の日本の数学教育界にかなりの衝撃と興奮をもたらしたと言われている。
◆現在の日本は,明治維新や太平洋戦争の敗戦のときのような大変革の怒涛の中にはないが,既存の体制や体系が徐々に,しかも確実に崩れつつある時代を迎えている。猛烈な勢いで押し寄せる情報化社会の到来,人間としての倫理をゆさぶる医学や生化学の進歩というグローバルな変動の渦の中にも巻き込まれている。
そうした中で,日本では平成14年度から新しい学習指導要領に基づく算数・数学教育が行われ始めた。くしくも,グラスコーでのペリーの講演から1世紀を経た時にである。そこでは,この新たな状況に立ち向かうために,どんな算数・数学教育への「こころざし」が掲げられたのであろうか。
平成9年の教育課程審議会の答申は,算数・数学教育の改善の重点を次のように述べている。
実生活との関連を考慮しつつ,ゆとりをもった作業的・操作的学習や問題解決的学習を通して,学ぶことの楽しさや充実感を味わいながら,数量や図形に関する基礎的・基本的な知識・技能に習熟させるとともに,数学的に考える力を身に付け,創造性の基礎を培っていく。
また,この基底には,ご存知のように,中央教育審議会の第一次答申で提示された「変化の激しいこれからの社会において[ゆとり]の中で」育んでいこうとする[生きる力]という合い言葉がある。それは次のように説明されている。
いかに社会が変化しようと,自分で課題をみつけ,自ら学び,自ら考え,主体的に判断し,行動し,よりよく問題を解決する資質と能力であり,また,自らを律しつつ,他人とともに協調し,他人を思いやる心や感動する心など,豊かな人間性である。
[生きる力]という言葉は,この内容に相応しくないと私は思っているが,それはそれとして,ここには「学ぶ」ことのあり方への指針が明確に示されている。これまで引用してきた「こころざし」に比べて,算数・数学教育で志向したい「数学的精神の高さ」とか「人間形成への寄与」という点で見劣りしないでもないが,これはこれで立派な「こころざし」と言うべきだろう。
問題は,こうした「こころざし」と教育の実態との乖離である。新学習指導要領における内容の3割削減は,「現代化」を否定した後,「もっと易しく,もっと少なく」といった路線をひた走ってきた日本の算数・数学教育の集大成と言ってもよいだろう。その結果,現場の教師が「数学」そのものと必死になって格闘する姿がみられなくなってきている。行政は,「学力低下」の指摘に右往左往し,それへの現実的な対応を現場の教師に求めている。こうした動向は,掲げたはずの「こころざし」を心許無いものにしつつあるように思えてならない。
◆ 難しい状況のもとではあるが,否,であるからこそ,算数・数学教育に「夢」を描きたい。描くべきだと思う。高き「数学的精神」を掲げつつ,算数・数学教育へのさらなる「こころざし」を追い求めていきたい。いくべきだと思う。