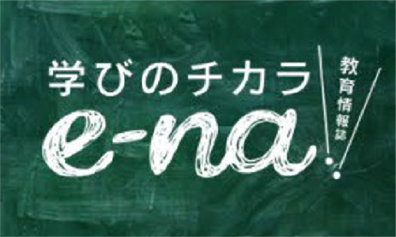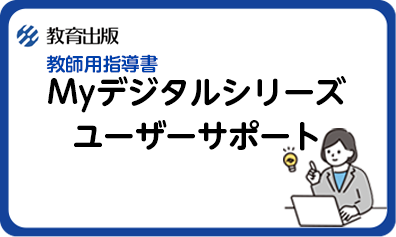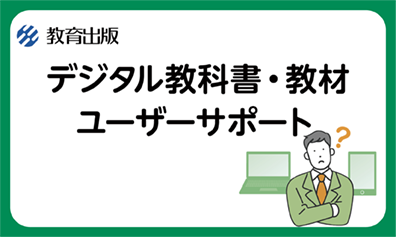道徳科における評価
道徳科における評価の考え方
小学校学習指導要領では,道徳科における評価の意義について,「児童の学習状況や道徳性に係る成長の様子を継続的に把握し,指導に生かすよう努める必要がある。ただし,数値などによる評価は行わないものとする。」と記されています。
また,学習指導要領解説では,「個々の内容項目ごとではなく,大くくりなまとまりを踏まえた評価とすることや,他の児童との比較による評価ではなく,児童がいかに成長したかを積極的に受け止めて認め,励ます個人内評価として記述式で行うことが求められる。」と記されています。
個人内評価をするためには,児童の学びの姿を見取り,児童一人一人のよさを見いだしていくことが必要です。教育出版の年間指導計画では,評価(見取り)の視点を,「授業での児童の学習状況を見取る視点(短期の評価)」と「長期的に道徳性に係る成長を見取る視点(長期の評価)」の大きく二つに分けて記載しています。短期の評価については,その授業でどんなところに着目するのかがさらにわかりやすいように,「道徳的価値の理解」「多面的・多角的に考える」「自分の生き方に結びつけて考える」の三つに分けて提示しています。これらは道徳科の目標に示された学習活動です。
教科化にともなう指導法等の改善によって,児童一人一人が活躍できる授業,児童の本音を引き出す授業,児童どうしが話し合って多様な見方・考え方に気づき,学びの意義を実感できる授業,そのような授業が実現できれば,児童の学びの姿を記録して評価するのは決して難しいことではなくなります。「指導と評価の一体化」は,全教科で求められる学習評価の考え方です。ともに授業をつくってきた児童たちに,「よさを認め,励ます」言葉を贈りましょう。
【評価の記述の例】
・道徳の評価は,ワークシートや学習状況の記録をもとにして,児童の成長の様子を総合的に判断し作成することになります。
・1年生の1学期の学習を通しての評価の記述としては,例えば,次のようなものが考えられます。
○道徳の授業では,あいさつについて,相手の気持ちに立って考えることができました。周りの人と気持ちよく接することの大切さに気づき,自分も実行していこうとする意欲がうかがえます。
○道徳の授業では,登場人物のとった行いについて自分の考えを積極的に発言する姿が見られました。「自分だったら...」と考えることで,自分自身を見つめようとする意識が感じられます。
○道徳の授業では,友達との話し合いを通して,自分とはちがういろいろな見方や感じ方があることに気づくことができました。相手の気持ちも考えながら行動しようとしています。