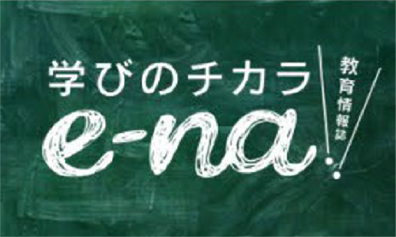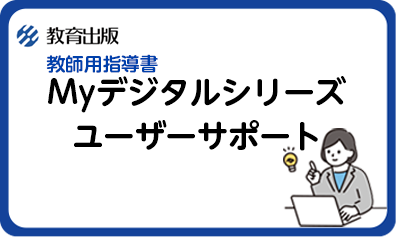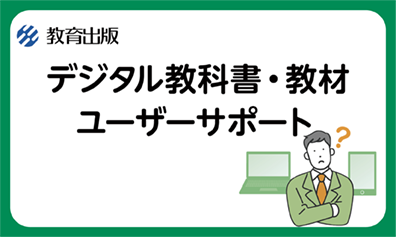こうしてみよう! Small Talk
第1回
Small Talkについての考察
1 Small Talkとは? その目的とは?
まず、Small Talkとは何かについて見てみましょう。『小学校外国語活動・外国語研修ガイドブック(平成29年7月文部科学省作成・HP掲載。以下『研修ガイドブック』)』には、以下のように記されています(p. 130)。
Small Talkとは、高学年新教材で設定されている活動である。2時間に1回程度、帯活動で、あるテーマのもと、指導者のまとまった話を聞いたり、ペアで自分の考えや気持ちを伝え合ったりすることである。また、5年生は指導者の話を聞くことを中心に、6年生はペアで伝え合うことを中心に行う。(下線は筆者)
さらに、同書(p. 84)で、下記のような目的(意図)が示されています。
Small Talk を行う主な目的は、(1) 既習表現を繰り返し使用できるようにしてその定着を図ること、(2) 対話の続け方を指導すること、の2点である。以下、それぞれの詳細について説明する。
(1)既習表現を繰り返し使用できるようにしてその定着を図る
これまでの外国語活動においては、児童が単元の新出言語材料に慣れ親しむことに重点が置かれていた一方で、複数単元を通じた系統性が弱く、言語材料の使用が単元ごとで完結している場合が少なくなかった。新学習指導要領に基づく外国語科の指導においては、言語材料の定着にも重点が置かれている。したがって、児童が、現在学習している単元及び当該単元より前の単元で学習した言語材料を繰り返し使用できる機会を保障し、当該言語材料の一層の定着を目指すことが求められる。
(2)対話を続けるための基本的な表現の定着を図る
「話すこと」によるコミュニケーションを行う際に欠かせないことが「対話を続けるための基本的な表現」である。我々が母語で対話をする際にも、相手の話した言葉を繰り返して話し手が伝えたい内容を確かめたり、相手の話したことに何らかの反応を示したりすることで対話は続くものである。(下線は筆者)
2 Small Talkを考え、進めるにあたっての留意点
実際には指導者が、上記の目的をふまえ、どのような内容を伝えたいのか、そのための言語材料として何を取り上げていくかということを基底として、Small Talkの内容を構成していくことになります。
したがって、Small Talkを考えるにあたって、以下の二点に注意したいと思います。
① Small Talkの意図(目的)を受け止めること
・テーマに基づいた「まとまりのある話」であること。
・5年生は「聞くこと」を中心とすること。
※ただし、対話形式(指導者の問いに答える形式)の活動を意図的に取り入れることで、学習活動が充実すると思われる単元もある。
・聞くことを通して「使えるようになる」(定着)を目指すものであること。
② 単元の目標との関連を重視しながら進めていくこと
また、必ずしも英語を専門としない学級担任が指導するケースもふまえ、Small Talkの表現を可能な限りシンプルにすることも併せて考えていく必要があるでしょう。
誰が指導するにしても、「自身のこと」を中核として構成するわけですから、そのためには、以下の二点について、学校全体での共通認識(方針)をもつべきではないかと考えます。
① 1 Lessonにつきどの程度の実施頻度が効果的かという方針
前述の『研修ガイドブック』(p. 130)では、Small Talkの実施頻度を「2時間に1回程度」(年間70コマの実施を想定すると、1 Lessonにつき8時間行う場合、4回程度となる)としていますが、頻度については柔軟に取り扱ってよいと考えたいと思います。
5年生では、3、4年生での外国語活動の実態によっては、授業の初めや単元の前半にSmall Talkを位置付けたり、既習表現の少なさなどから、多くの語彙や表現をともなうSmall Talkを実施したりすることは、難しいかもしれません。そこで、頻度もふくめ、どの指導段階で実施するのが効果的なのかを考えることが大切となります。
② 既習の言語材料や表現について、どのような内容をどういった系統性をもって取り上げていくのかという方針
その単元で学習した言語材料を「復習する」という取り上げ方が中心になってしまわないかという危惧があります。当該の単元の学習で取り組むアクティビティとSmall Talkの目的の違いを、指導者(学校の体制としても)が意識できるかどうかがカギと言えるでしょう。
また、聞くことに重点を置いた単元構成にするのか、さらに、指導者と学習者との対話活動に重点を置いた活動を盛り込むのか、といった選択をすることも大切です。
第2回より、『ONE WORLD Smiles』を使った指導で私自身がSmall Talkを構成していくとしたらどのように進めるのかについて、単元ごとに、その一例を示していきたいと思います。