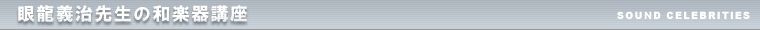 |
|
|
 |
 |
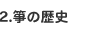
箏の伝来
奈良時代,管絃(雅楽)合奏の楽器として中国から伝来し,平安時代には貴族たちが愛好しました。
例えば,源氏物語には「そうのこと」「きんのこと」「びわのこと」等の表現があります。
鎌倉時代になり貴族社会の没落とともに衰退しましたが,室町時代に九州の僧“賢順”が雅楽から離れた箏独自の音楽分野を創始しました。
江戸時代前期には上方で,賢順の孫弟子にあたる“八橋検校”が調弦法の改革や三味線音楽との融合を図り,この楽器の発展の基礎を築きました。
その後,“生田検校”によって生田流が興り,江戸時代中期には江戸で,“山田検校”が山田流を興し,今日に伝わる二大流派のもととなりました。
現在は,それ以外の流派も存在します。
中国では2500年以上前には既に,現在の箏とほとんど同じような楽器が存在しました。
時代や地域によっていろいろな大きさのものがあったようです。
1978年に発掘された古墳(曽侯乙墓)からの出土(二十五弦箏)によって確認されていますが,それ以上どのくらいさかのぼることができるのでしょうか。
中国では高貴な楽器として位置づけられていたと思われます。そこで,楽器の部分名称に皇帝を象徴するといわれる「(龍)竜」が用いられたのでしょう。
そしてまた,各弦の名称には,人間が社会生活を営む上で大切な意味を持つと思われる文字が当てられました。
箏の同属楽器
中国から伝来しましたが,現在の中国にはわが国の箏と同じ楽器はありません。
中国で一般的に使われている楽器は二十一弦で,スチール弦になっており「古箏(グージォン)」と呼ばれています。
奏法も音色も日本の箏と異なります。
中国人古箏奏者の蘇宇虹(su yu hong)さんに,「なぜスチール弦にしたのか?」と尋ねましたら,「経済的だから」と,ただ一言・・・。
現在の中国では三弦も琵琶も二胡も全てスチール弦になっています。
中国の人々は,比較的,実利重視の考え方のようです。
|
 |
韓国には十二弦の箏が現在使われています。
伽耶琴(カヤグム)ですが,わが国の箏よりひと回り小さく,厚みも薄いつくりです。
あぐらのような座り方で,竜頭の部分を膝の上にのせて演奏します。
弦の張り方はわが国のように強くせず,押し手による余韻の変化を多用する音楽表現をします。
ちなみに,“琴”(きん)と“箏”は全く別の楽器です。
柱を用いない方が琴。現在使われている琴は七弦のもので,「古琴(中国名グーチン)」と呼んでいます。
これは現在の中国でもわが国でも全く同じ楽器が使われています。
左手で弦の一部を押さえて音程を調整して演奏します。
余韻が響いている間に左手をずらすと,塩梅(えんばい=ポルタメント)を多用した音楽表現が可能になります。
わが国の「一弦琴」も同種の楽器ということができます。これはハワイアン・ギターの奏法に似ています。 |
|
 |
| |
|
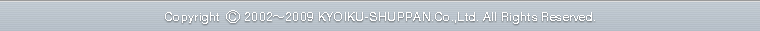 |
|