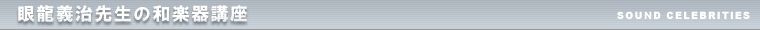 |
|
|
 |
 |
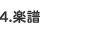
縦譜
箏譜は流派によっていろいろな楽譜が用いられています。
基本的なものは漢数字を用いた奏法譜(糸譜)で,縦書きのものと横書きのものが使われていますが,その書式は流派によっていろいろあります。
最近は教育現場に対応する目的で,算用数字を用いたものや,五線譜との併記譜が用いられるようになり,出版物でも多く見かけられるようになりました。
奏法譜は弦名を表現する楽譜ですから,絶対的な音高は表現しません。
そこが五線譜との大きな違いです。
従って同じ楽譜を用いても調弦の仕方によって実音は異なります。
邦楽の理論上の基準音は洋楽のD音(レ)に近い「壱越(いちこつ)」音ですから,基本的な平調子は一の弦がD音になります。
しかし,教育現場での利便性からすると,一の弦をE音にする方が妥当であると思います。(五線譜上ではハ長調と同じ表記になるので便利です)
ただし,邦楽界ではD音にこだわる向きもあるようです。
なお,普通に弦を張った箏では低い音の限界はd音(ヘ音記号・第3線のレ)でしょう。
そして,高い音の限界は3点d音(ト音記号・上第2線のレ)くらいでしょう。高い方はもう少し上まで可能ですが余韻がなくなり,響きも良くありません。
この音域内ならばどのような旋法にも,どのような調にも自由に対応できる,大変便利な楽器です。
ちなみに,十七弦箏は全体に1オクターブ低いと考えればよろしいでしょう。
縦譜
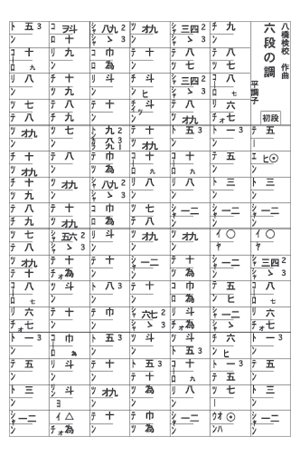
横譜
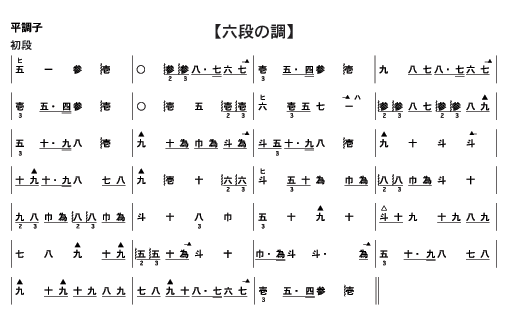
五線併記譜

|
 |
| |
|
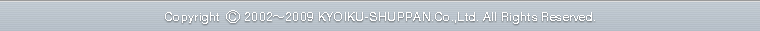 |
|