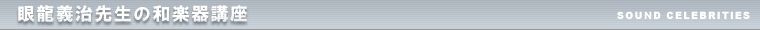 |
|
|
 |
 |

弦名
箏の弦名は低音(体から離れた位置にある弦)から順番に,一,二,三,四,五,六,七,八,九,十,斗(と),為(い),巾(きん)となっています。
最近教育現場では1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 のように算用数字を用いることも行われています。
ただし,11,12,13は,1,2,3との見間違えを防ぐために,斗,為,巾はそのまま用いる場合が多いようです。
本来は13本の弦に,仁,智,礼,義,信,文,武,斐,蘭,商,斗,為,巾の漢字が当てられていました。
現在の斗,為,巾はそこからきています。
調弦法の例
| |
※長音階は1オクターブと6度,半音階は1オクターブしか音域がとれません。したがって,このような調弦を用いて合奏する場合は,パートによって音域をずらし,全体として音域を広げる配慮が必要です。 |
|
 |
| |
|
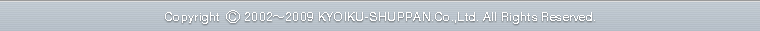 |
|