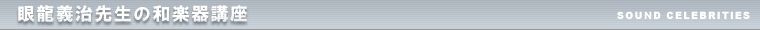 |
|
|
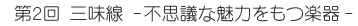 |
 |
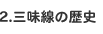
三味線の伝来
三味線がいつ,何処に入って来たのかは正確にはわかっていません。諸説ありますが,16世紀中ごろ(永禄年間),琉球から当時の貿易港である堺港に入ったと言うのが一般的です。
琉球から入ったということから,現在の沖縄の三線(さんしん)に近い物であったろうと思われます。それを当時の琵琶法師が演奏し始めたと考えられています。
その後いろいろな改良が加えられ,数十年後には現在の三味線に近い物ができたようです。特にサワリの工夫は画期的なものでした。これは琵琶の響きに近づけたいとの欲求から工夫されたものであろうと思います。また,大きな撥で演奏する方法も琵琶からの影響であることは明らかです。それまでは琵琶を伴奏としていた「語り物」(浄瑠璃)を三味線がとって替わることになり,発展の礎となったと思われます。
そのことに織田信長が関わったとする説もあります。新しいことに非常に積極的であった信長としては,あり得ない話でもないように思います。ちなみに,彼はキリシタン音楽も直接聴いており,大いに興味を示したと言われています。
箏も琵琶も使用できる階層が決まっており,まだ庶民が手にできる楽器ではありませんでした。そこに新しく入ってきた三味線はそのような制約がなく,一挙に庶民の手に広まったものと思います。
そのことが一方では,三味線を賤しい楽器であるかのように位置付けをする人々が現れることにもつながったものと思われます。このような考え方は最近までありました。
三味線の同属楽器
言うまでも無く,沖縄の三線が最も近い同属楽器です。楽器自体の大きさ,サワリの有無,撥の使い方等が大きく異なります。もちろん,それらは音楽的表現の要求の違いからきています。
琉球の三線は中国から入ったものであることは間違いないと思います。
中国では元の時代から三弦(サンシエン)が使われていました。そのルーツはペルシャのセタールであろうと言われています。(セタールは3本の弦と言う意味) 沖縄の三線より中国の三弦の方が,形や大きさは三味線に近いと言えます。
ただし,中国の三弦は撥を使わず,指に義爪をテープで固定して演奏します。
また,現在では弦は全てスチール弦になっています。
もっとも,現在の中国では箏も琵琶も月琴も殆どスチール弦を使うようになっています。
それは経済的な理由によるものです。中国の人々は非常に現実主義的な考え方をします。そのあたりは日本人と大きな違いがあるように思います。
|
 |
|
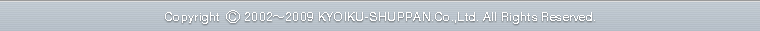 |
|