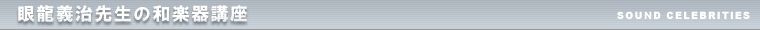 |
|
|
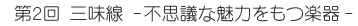 |
 |

三味線にはいろいろな種類があることは先に述べましたが,これ以降は中棹・細棹を前提として話を進めてまいります。
なお,五線譜で記譜する場合は,実音は1オクターブ低くなります。洋楽器のバスクラリネットと同様の扱いとなる訳です。三味線の調弦は「本調子」「二上がり調子(二上りとも表記)」「三下がり調子(三上りとも表記)」の3種類が基本的なものです。それ以外にも特殊な調子はありますが,ここでは基本的なもののみを取り上げます。
なお,後の2つのことを一般的には単純に「二上がり」「三下がり」と言います。
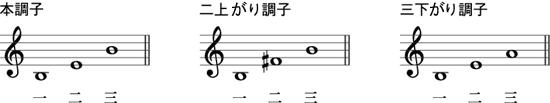
三味線の調弦は絶対音を表わす訳ではなく,相対的な音程関係を表現します。一の弦は最低a音から最高1点d音位の範囲で用います。低い音域の調弦は古曲では多く用いますが,現代曲では高い音域の調弦を用いるのが一般的です。
特に現代曲の合奏の場合は高い方が良く響き,他の楽器とのバランスも良くなります。普通合奏曲の場合は他の楽器との関連で,独奏曲の場合は曲想によって高低を決めます。低過ぎると全体的に響きにハリがなく,高過ぎると三の弦が切れやすくなります。
このように調弦の幅があることは洋楽器では考えられないことです。これは絹糸弦を用いていることのメリットとも言うことができるでしょう。
|
 |
| |
|
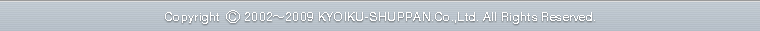 |
|