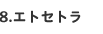
教育楽器としての三味線
三味線は自分で音を作りながら演奏する楽器です。そして,ギターのようにフレットがありませんので自分の音感で音を作らなければなりません。その点が少し難しい楽器ともいえます。また,演奏中に弦が緩むこともあります。
プロは演奏中でも常にピッチを調整しながら演奏しますが,子どもたちがそこまでになるには相当の訓練が必要です。
選択授業や部活の場合は大いに活用してほしい楽器ですが,教科授業の場合は使いこなせるほど十分な時間が取れない場合が多いと思います。
そのような場合はリズム楽器として扱うと比較的易しく取り入れることができます。合奏曲の場合は開放弦を上手く活用してリズムセクションを担当させるとよろしいでしょう。
そして,あまり音の動きの激しくない部分で,適切に旋律を担当する部分を入れるような編曲をすると,子どもたちも大喜びで参加します。
三味線はこんな楽器
サワリについて
サワリは倍音と共振の現象を巧みに応用したものです。一弦のみ上駒に乗せず,かすかに棹に触れるような構造になっています。そのために棹には独特の工夫がなされています。
このような構造は沖縄の三線にも中国の三弦にも見られません。我が国で考えられたことです。いつ,だれが発明したのかは特定されていません。
吉川英史氏の研究によると享保年間(1716~)には上駒に3本の弦を乗せたものが存在しました。
文献的に一弦を上駒から外すことが明確になるのは宝暦7年(1757)のことです。ただし,当初はサワリのあるものとないものが並行して使われていたであろうと推測されます。そして,総合的に要約すると寛永前後(1624)上方の浄瑠璃三味線の演奏家が始めたことであろうとしています。私は琵琶の音に近い効果を求めて考案されたものであろうと考えています。
明治時代,棹に特殊なネジを通して調整できるサワリが発明されました。「吾妻サワリ」「大阪サワリ」「都サワリ」等の名称が使われました。今日では更に改良を加えたものが広く使われています。
日本人の美意識は,自然との調和を非常に大切にします。それは音楽においても同様であり,純粋な楽音だけでは満足できません。
そこで,サワリによって一種の噪音を音楽表現の中に取り入れたのであろうと思います。尺八でもイキを漏らした奏法を用いますし,箏でも爪で弦を擦る奏法を用います。日本人が大切に考えている「わび」「さび」に通じる感性であろうと思います。ちなみに,ヨーロッパの楽器は純粋な楽音だけが,なるべく容易に出せるように改良されてきました。その結果どの楽器も非常にメカニックな姿になりました。
サワリの原理をピアノで実験してみましょう。低いCの鍵盤をゆっくり押さえ,ダンパーを開放します。その状態を保ったまま,高い音域で倍音に当たる音を強く打鍵します。するとCの弦が共振して鳴り出します。
仮に1点gを打鍵すると1点g音で,2点e音を打鍵すると2点e音で鳴り出します。倍音に当たる音ならば共振する訳です。この原理により,三味線は二,三の弦を弾いた時,倍音に一致する勘所ではサワリが鳴り出します。
日本の旋法で創られた曲の場合は倍音に当たる音が多く現れます。従って,ほとんど常にサワリが鳴っているように感じられる訳です。また,調弦をする時もサワリが鳴るのを確認しながら行えば,調弦がしやすい訳です。
勘所(ツボ)について
三味線は大変棹の長い楽器です。おそらく全体のバランスからすると世界一長い楽器と言えるのではないでしょうか。そのために一つのツボから隣のツボまでの間隔が長くなり,隣の指をどんなに拡げても届きません。
そこで,人差し指(Ⅰ)を腕ごと素早く移動して次のツボを押さえなくてはなりません。このことが,難しい楽器にしている一因でもあろうかと思います。
ヴァイオリン等ですと腕を移動せずに4本の指を順番に押さえ,更に高音域になって初めて2nd.ポジションに移動します。教育現場で活用する場合は開放弦を中心とし,ツボを使う音は補助的に用いるよう配慮するとよろしいでしょう。そのためには曲によってどの調弦法を活用するかを見定めることが大切です。
メンテナンス等
保管について
弦はその都度少し緩め,特に一弦はサワリ溝から外してください。柔らかい布(専用のものがあります)で,拭いて(特に棹はよく拭く)ください。駒は外します。撥は撥先を傷めないようカバーをかけます。
ハードケースの場合は必ず中の紐を結んでください。(万一ケースを倒したり,ぶつけたりすると中で傷むことがあります) ソフトケースは上下逆にならないように気をつけて入れ,倒れないよう配慮の上,立てかけて保管するとよろしいでしょう。(そのような収納箱を工夫している方々がいらっしゃいます。ねかせて床に置くとつい上に物を置いたり,重ねたりする心配があります) 一挺毎のスタンド式の場合は全体に埃がかからないよう,布をかけておくとよろしいでしょう。
防水式のケースに長期間入れて置くのはよくありません。また,普段は「三つ折れ」の棹は分解せず,そのまま保管するべきでしょう。
調弦について
中学校では,教師の楽器のみ調弦を済ませておき,教師が一弦ずつゆっくり弾きます。生徒たちはそれを聞きながら一斉に音を合わせます。この方法ならば何挺あってもほぼ同じ時間で調弦できます。
初めは手間取りますが慣れるとかなり早くできるようになります。合わせるのに手間取っている生徒がいる場合,教師が適切に声をかけてあげると,更に良い指導ができます。しかし,小学校ではこの方法はいささか困難でしょうから,やはり教師が全て行わなくてはならないでしょう。
破損等について
弦が切れた場合は教師が自分で張り替えられるよう慣れてください。最近は合成繊維の弦もあり,切れにくくはなっていますが,三の弦はどうしても切れやすいものです。
皮が破れたら場合は,専門業者に修理を依頼しなければなりません。皮も最近は合成皮革のものが開発され,扱い易くなりました。
撥については,教育現場で使う場合はほとんど化学合成品であろうと思います。鼈甲製品の場合,長期間使用せず保管する時は防虫に気をつけてください。なお,撥は先を傷めやすいし,また,子どもたちが持ったまま駆け出したりすると危険なので十分に気をつけてください。
三味線を用いる音楽分野について
今日,一般に邦楽器と言われている楽器の中では最もおそく伝来した楽器です。にもかかわらず,最も多くのジャンルで使われている楽器でもあります。「にもかかわらず」ではなく,「であるからこそ」かもしれません。と言いますのは,他の楽器は当時の社会機構の中で,それぞれ使用できる階層が決まっており,庶民は使用できませんでした。ちょうど織田信長がそれまでの社会機構を改革しようとした時代に三味線は伝来しました。しかも信長自身も三味線を好んだと言われています。そのような絶妙なタイミングのもと,一気に庶民の中に広まっていったのではないかと,私は考えています。
現在,雅楽と能楽以外のほとんどのジャンルで使われていると思います。以下,大まかに歴史的にたどってみましょう。現在廃れてしまったジャンルは原則として省きます。
1600年代
☆うた物:三味線組歌,地歌(箏と融合),端唄(今日の端唄とは別物),長唄(歌舞伎音楽との結びつき)
☆かたり物:浄瑠璃(江戸節,外記節),義太夫節,一中節
1700年代
☆うた物:地歌,端唄物(地歌分野の中での端唄),長唄,荻江節
☆かたり物:豊後節,常磐津節,河東節,富本節,薗八節,新内節,繁太夫節
1800年代
☆うた物:地歌(手事物の発達),長唄,端唄,うた沢節,小唄,浪花節
☆かたり物:清元節
以上の他にも沢山ありますが,主なものを上げてみました。例えば民謡も三味線を伴奏楽器として盛んに用いています。しかし,いつごろから用いられるようになったか定かではありません。津軽三味線は,義太夫節三味線と津軽民謡が結びついて生まれました。歴史的にはそれほど古いことではありません。地歌箏曲は今日では箏が主で三味線が従のように思われていますが,本来三味線音楽として上方に興りました。
三味線が如何に日本人の心を捉える音をもっているかが,これらによって十分に理解できると思います。ただし,どのジャンルにおいてもごく最近まで,ほとんど伴奏楽器として発展してきました。これを独奏楽器としても,もっともっと発展せるべきではないかと私は考えています。その可能性を十分に備えている楽器ですから。
浄瑠璃について
語り物音楽は,初めは琵琶を伴奏楽器としていました。盲僧琵琶が最も古いものと考えられています。琵琶を弾きながら地神,荒神(火の神),水神等の祭りごとを行ったり,仏教説話をやさしい言葉で琵琶を伴奏に語って廻ります。現在は宮崎県在住の永田法順師がただお一人のようです。
後に平家琵琶が興りますが,いつから始まったかは正確には分かりません。初めの頃は盲僧琵琶の法師が,合戦で亡くなった人の鎮魂のための軍談を語っていたのであろうと言われています。平家琵琶のテキストである「平家物語」の成立そのものが正確には分かっていません。「平曲」とも言いますが,この分野の音楽は「うたう」とは言わず「語る」と言います。
浄瑠璃は1500年代前半に興り,琵琶を伴奏にして語っていました。「浄瑠璃姫」の物語を語ったのが最初であったため,浄瑠璃と言われるようになったとする説もありますが,はっきりしません。
1500年代後半三味線が伝来し,琵琶に替わって三味線が使われるようになりました。上方での義太夫節と一中節から始まり,後に江戸の発展と共に双方で競い合うかのごとくに大きな展開をみるに至りました。優れた演奏家が現れる度に,音楽表現法が微妙に異なり,新しい浄瑠璃の名称(派)が生まれました。今日では,浄瑠璃は三味線による「語り物」音楽の総称のようになっています。「浪花節」を含めて記述した音楽書はあまり見かけませんが,内容的には浄瑠璃に含めて考えてもかまわないと私は思っています。(現実には浄瑠璃とは言っていませんが)
|