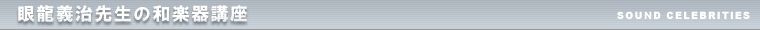 |
|
|
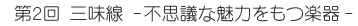 |
 |
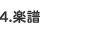
現在三味線の楽譜はいろいろな書式のものが使われています。大きく分けると縦書き譜と横書き譜があります。
ここでは縦譜は,主として地歌で使われているマス目式のものを,横譜は主として長唄で使われている文化譜を例示いたします。
歴史的には,寛文4年(1664)京の秋田屋が出版した「糸竹初心集」が最も古い楽譜とされています。もちろん縦書き譜で,平仮名で歌詞を書き,その右側に片仮名で勘所と奏法を同時に記しています。唱歌(口三味線)の一種と言うことができます。
勘所(ツボ)の一覧表
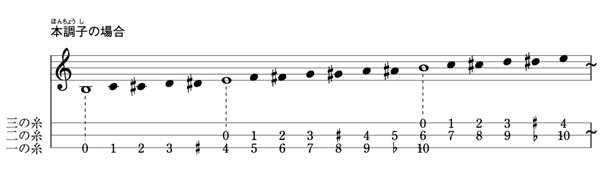
縦譜
勘所を数字で表現します。一の弦はイ一、イ三……。二の弦は一,三……。三の弦は1,3……のように表わします。音価はマス目で表わし,1マスが1拍です。「ス」はスクイ撥,「∧」はハジキを表わします。
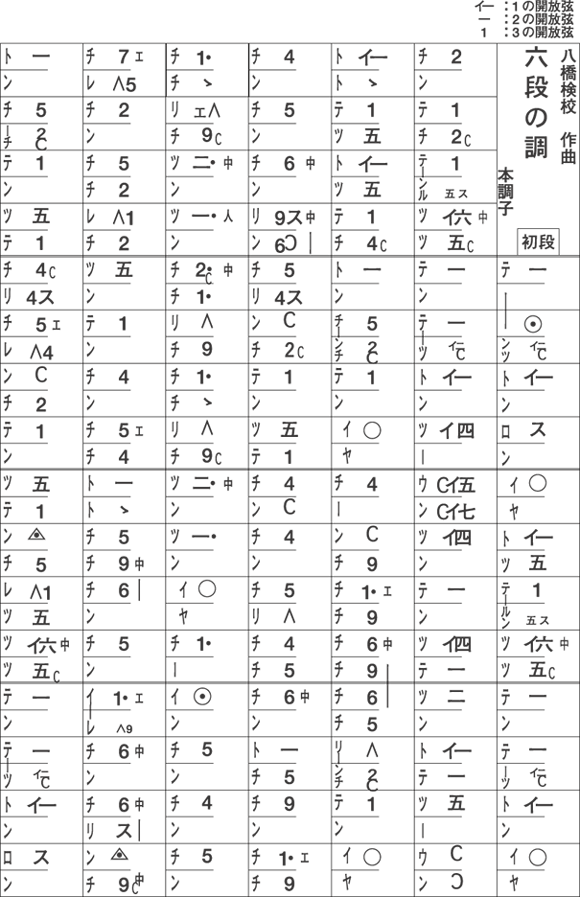
横譜
勘所を数字で表現するのは縦譜と同じです。弦の違いを3本の線で表現するところがこの楽譜の特徴です。ギターのタブ譜と同じ考え方になり,五線譜に慣れた者には分かりやすいとも言えましょう。
3本の弦が3本の線で使い分けられますから,数字は算用数字のみで足ります。スクイ撥は「ス」で,ハジキは「ハ」で表わします。
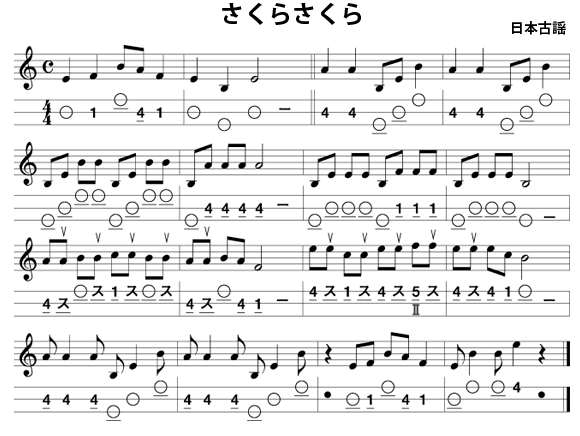
|
 |
| |
|
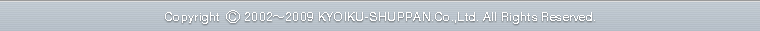 |
|