| |
|
|
|
|
| |
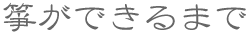 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
胴の木目には,「板目」「柾目」の二種類があります。
板目のものが一般的です。
柾目のものは原木がよほど太くないと作れませんので高価なものになります。
また,木目が渦巻き型になっているものがありますが,これは大変珍しいもので特に「玉杢」(たまもく)と呼んでいます。
長さは約180cmで,幅は竜頭部分が約25cm,竜尾部分が約23cmで中央部がやや膨らんでいます。
厚さは竜頭部分が約5cm,竜尾部分が約4cmになっています。胴全体は弓なりに湾曲しています。
これは弦の張力に対する強度を高めるためです。 |
 |
 |
 |
|
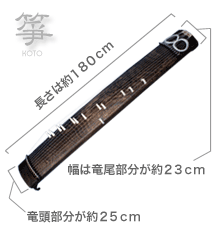 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
胴の内部を箱状にくり抜き,裏板を張りますが,その方法には「ベタ付け」(並甲)と「トメ付け」(くり甲)があります。
くり甲は表板と裏板の継ぎ目がほとんどわかりません。 |
|
胴の内側には6本の「ハリ板」が張られ強度を高めています。
また,裏板の両端には音穴が2個所開けられています。(音穴は糸締めのためにも使われる)。 |
|
| |
|
|
 |
|
| |
|
|
|
|
| |
胴全体は焼きコテで焼き上げ,さらに磨きをかけて,あの美しい桐の木の肌合いを出します。
最近は化学薬品で処理したものもあります。
|
|
竜角,雲角,竜舌,四分六(しぶろく),柏葉(かしわば)尾絹(おぎぬ),心座,脚等を取り付けて完成します。 |
|
| |
 |
|
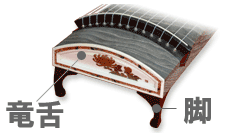 |
|
| |