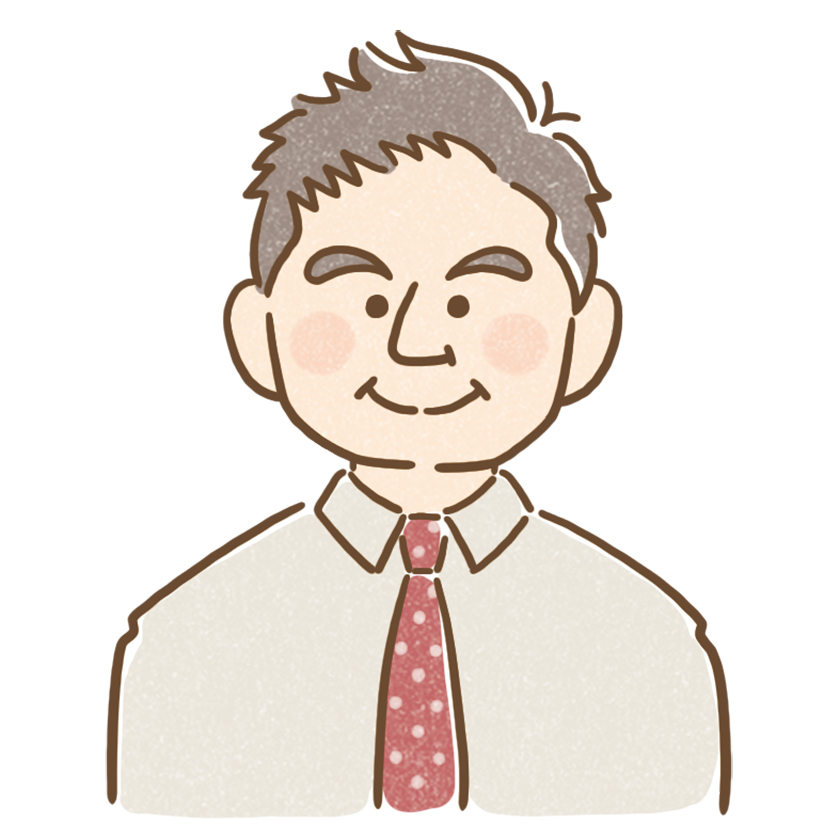第10回 みんなが伸びる学校と、先生の働き方
広島大学大学院人間社会科学研究科准教授
ハヤシさん:カトウさん、ついに最終回だね。
カトウ先生:なんでキャラクターがそんなことを知ってるの?(笑)。
ハヤシさん:最初の頃、カトウさんはミンさんが来るということをずいぶんと「困った」「大変だ」と言っていたけど、途中から言わなくなった気がするよ。
カトウ先生:確かにそうだね。最初は自分自身がかなり「壁」をもっていたんだと思う。
ハヤシさん:壁?
カトウ先生:たぶん、ミンさんを「困っている子」「つまずいている子」というふうに僕が勝手に思っていて、ちゃんと見ていなかったのかもしれないなと思って。
ハヤシさん:ああ、最初の頃に言っていた「できなさ思考」 というやつだね。
カトウ先生:うん。それと、なんというか、実際にいろいろやってみたのが楽しかったんだよね。
ハヤシさん:楽しかった?
カトウ先生:うん、もちろん大変だとも思ったけれど、それ以上に、ミンさんだけじゃなく、クラス全体の授業や、学校全体のことを考えるきっかけになって、あれこれと工夫するのが楽しかった。「お、これが出てきたか」「こうしてみたらどうなるか」みたいなことがたぶん楽しかったんだよね。
ハヤシさん:なるほどねえ。それって、教師の仕事の根幹なのかもしれないね。
カトウ先生:そうだね。校長先生に言われたよ。「先の見えない不安を楽しむのも教師の大切な資質ですよ」って。それは確かにそうだなと思う。
ハヤシさん:そもそもミンさんのような外国につながる子どもだけじゃなくて、いろいろな子どもにそれぞれつまずきもあるし、のびしろもあるもんね。
カトウ先生:そうなんだよ。結局ミンさんだって、これから高学年、中学生、高校生、大学生や社会人、大人になって人生を歩んでいく中で、きっといろいろな壁にぶつかると思う。その中で、僕らができることは、壁をなくすこと以上に、こうじゃないかああじゃないかと工夫しながら、壁を越えることを一緒にやっていくことかなと。少し先を見ながら。
ハヤシさん:先生の仕事って、最近「忙しい」といわれるけど、負担にならない?
カトウ先生:そうだね、でも、こういう感じで校長先生や日本語の先生、他の先生たちと一緒に考えることには、別に負担感はないなあ。むしろ、やっぱり楽しいんだと思うよ。教師冥利に尽きるという感じ。
ハヤシさん:「先の見えない中で楽しみながらあれこれやってみる力」って、それこそが先生の専門性のひとつなのかもしれないね。
カトウ先生:そうだね。誰かに「お任せ」してしまうのではなく、少し先をぼんやり見ながら、それぞれができる範囲で、というのができると負担にならないし、それがいちばんの「働き方改革」だと思うな。結果それは、子どもにとっても負担にならないし、子どもは、先の長い人生の中で少しずつ育っていけばよいのだから。
ハヤシさん:まだまだ答えは見えないけれど、結局ずっとあれこれ考えて、そうした専門性の感覚を磨いていくことが大事なんだね。
10回に渡る連載も今回が最終回です。今回は「教師の成長」「教師の働き方」ということに焦点を当てています。外国につながる子どもたちの教育のことは、ここ数年の間でもずいぶんと社会の中で認知されるようになりました。
外国につながる子どもたちの抱える課題をめぐって、具体的な取り組みがたくさん報道されるようになりました。ただ、全体的に眺めてみると、その多くは「困っている子ども、つまずいている子ども」の姿に焦点が当たり、日本語の指導にあたる先生がキーパーソンになって取り組み、子どもたちもがんばっているという物語が描かれ、そして日本語指導の充実がメッセージとして伝わってくることが多くあります。もちろん、それも1つの物語でしょう。
ただ、学校という場所は組織で動く場所であること、外国につながる子どもに関わらずすべての子どもたちを育てる場所でもあることから、「1人の日本語指導の専門家を配置する」ことがそのまま解決になるわけではありません(第2回参照) 。
ハヤシさんが言うように、確かに学校現場には、今、「人手がない」「忙しい」という言葉が渦を巻いています。それは事実としても、その解決は「専門家を入れて分業する」ということだけでは、恐らく解消しないでしょう。教員どうしのコミュニケーションが不足し、お互いに「時短」「効率化」という中で対話や新しい発想の交流ができないようになってしまえば、職場は対話のない、気ばかりを遣い、指示どおりに仕事をこなす単純労働的なものになっていきかねません。しかも答えは見えず、結果それは「働き方改革」にもならないでしょう。
教師の本来の仕事を思い返してみれば、「人を育てる」という複雑な面をもっており、常に「先が見えない」ものです。校長先生がカトウ先生に語ったように、「先の見えない不安」を楽しんでいくことができるような職場をつくっていくことが何よりも重要です。
不安の解消のために専門家を入れても、それが分業と効率化の発想であるならば、すぐに次の不安が出てくるはずです。もちろん、専門家を入れること自体はよいことです。しかし、そこには「一緒に考える」「ヒントを得ながら自分ごととして考える」ということをお互いにできるコミュニケーションが必要です。
今回の連載では、第7回の学校づくりの話あたりから校長先生の姿もクローズアップされてきました。目の前の外国につながる子どもの教育は、実のところ日本語指導という「授業」の問題以上に、学校全体の「カリキュラム」(学校のあり方や全体の教育のつくり方)の問題だからです。全体の学校設計しだいで、いろいろな子どもたちの参加や自己実現のあり方も変わってきます。これを、日本語指導という授業レベルの支援の問題にしてしまうと、日本語指導がない場所では何もできず、日本語指導者が外れればそれでおしまいという状態になってしまいます。
外国につながる子どもの人数に関わらず、「カリキュラム」という学校全体の問題として考えていくと、学校をどうしたらよりよいものにしていけるか、その中で教師はどう働いていけるかという問題につながります。そこで重要となるのは、第7回の「活躍の場をつくる」、第8回の「地域と連携する」、第9回の「評価のあり方を考え直す」というような、現実の問題に合わせて柔軟に発想を変えていくことです。
今、学校は「外の声」に敏感で、それを気にするあまり、教師たちが自信をなくし、ついつい自縄自縛になってしまいがちです。しかし、やはり思い出すべきは、教師たち自身の本来の資質は「子どもたちと一緒におもしろがれること、そして工夫の中でちょっとした成長を喜べること」であり、それは今も昔も変わりません。
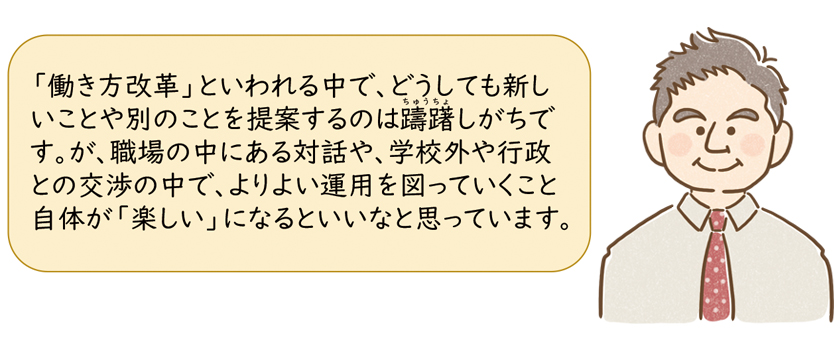
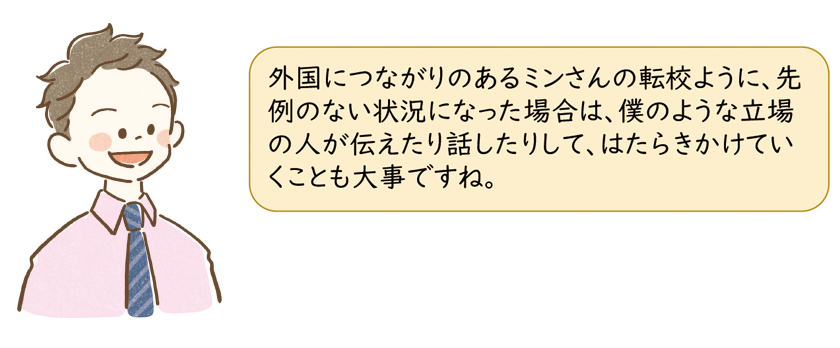
顔の見えない匿名の人たちに対する説明責任ではなく、目の前の子どもたちに対する応答責任を大切にしたいものです。そして、現状の中にあるマンネリに向き合い,何ができそうかを考えながら現状を打開する方法を探して、学校運営や学級運営ができていくといいですね。それはきっと、教師たちにとっても楽しいし、その姿勢は子どもたちの楽しさにもつながっていくはずです。
今回の連載における、カトウ先生、ハヤシさん、ミンさん、日本語の先生、校長先生は、ある意味の「理想」ではあったかもしれませんが、「みんなが伸びる学校」は、そうした「楽しむこと」の中にあるはずです。
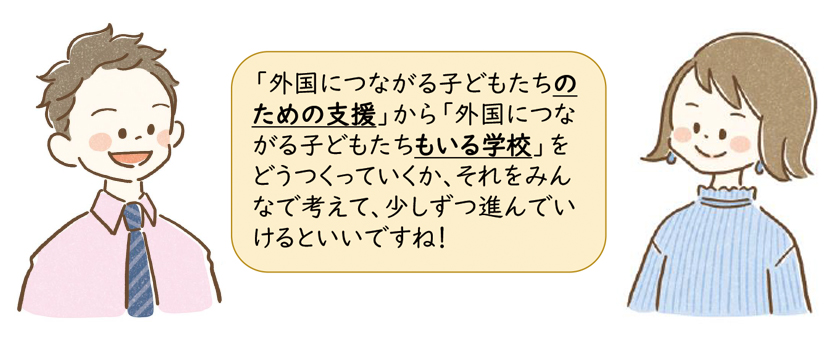
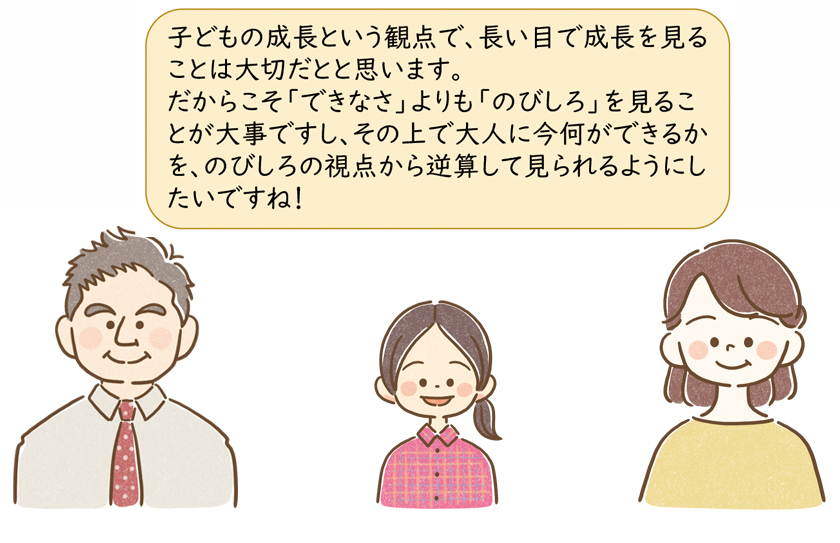
【著者プロフィール】
言語的文化的に多様な子どもたちをめぐって、ことばと文化の共生の点から力のある授業と学校をデザインしていこうとする教師教育の仕事をしています。