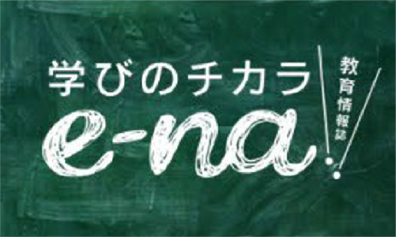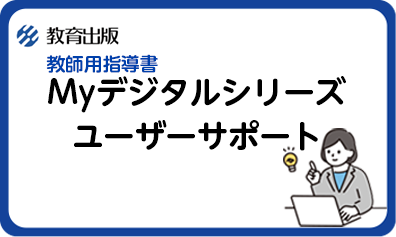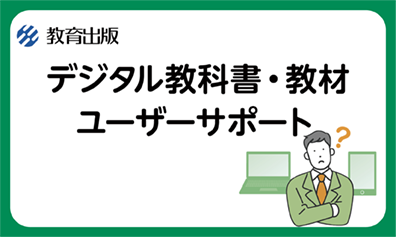第2回 AIのしくみを教えて!
みなさんは、「AIってどうやって動いているの?」とふしぎに思ったことはありませんか?
前回は、「AIはただの道具じゃなく、私たちがどう向き合うかが大事」という話をしました。
今回は、AIがどんなしくみで動いているのか、一緒に考えてみましょう。
AIはどうやって学んでいるの?
今のAIの多くは「機械学習」というしくみを使っています。
これは、「たくさんのデータを見て、どういうときにどうなることが多いか」ということをもとに、新しい問題の答えを予想する方法です。
たとえば、「犬と猫を見分けるAI」を作るとき、犬や猫の写真を何千枚、何万枚と見せます。
AIは、「犬は耳がとがっていることが多い」「猫は顔が丸いことが多い」など、写真の中にくり返し出てくる特徴を数字で表して、犬か猫かを当てられるようになります。
AIはデータの中で、「この特徴があると犬である確率が高い」という数字(統計的な関係)を計算しているだけです。
ニューラルネットワークのしくみ
AIの中でも特に強力なしくみが、「ニューラルネットワーク」です。
これは人間の脳の神経細胞(ニューロン)がたがいにつながって情報をやりとりするしくみをまねして作られました。
簡単なニューラルネットワークでは、写真の数字データを入力し、それぞれに「重み(どれくらい大事か)」を掛け算し、それを足し合わせて答えを出します。
けれど今のAIは、単純な1回の計算ではなく、何層もの中間層(隠れ層)を通じて情報を処理することで、より複雑な特徴を見つけられるようになっています。
たとえば
最初の層 → 写真の中の小さな線や角を見つける
次の層 → それを組み合わせて目や耳の形を見つける
さらに次の層 → 顔全体の特徴を見つける
こうした層が深くなるほど、AIは複雑なものを理解しているように振る舞えるのです。
学習の流れ
では、このたくさんの重みはどうやって決めるのでしょう?
AIは最初、重みを適当に設定します。最初は間違えて当たり前です。
たとえば、猫の写真を犬と間違えたり、うさぎと判断してしまうかもしれません。
そこで「正解は猫だよ!」と教えると、AIは「じゃあどの部分の重みを変えたら、次は正しくなるかな?」と少しずつ重みを調整します。これをくり返すことでだんだん精度(正解率)が上がります。
こうして自動調整された重みの多くは、最終的に人間にとって直感的に理解できる意味をもつとはかぎりません。
AIは人間みたいに考えているの?
ここがとても大事なところです。
人間、特に赤ちゃんは、体験や感覚を通して世界を学びます。
手でさわったり、においをかいだり、口に入れてみたり、「うれしい」「びっくりした」といった気持ちや、まわりの人とのやりとりを通して、少しずつ「わかる」「知っている」という感覚を育てます。
一方、AIはそうではありません。
AIは、今までに見せられたデータの中で、「どんなときにどんな数字が出やすかったか」をもとに、「たぶん今回もこうだろう」と計算し、数字の上でいちばん合いそうな答えを選んでいるだけです。
その計算の結果が私たち人間の期待と同じになると、「AIはわかっているみたいだ」と私たちは感じます。
でも実際には、AIは意味を理解したり、理由を考えたりしているわけではありません。
だから、AIと人間では「学び方」も「答えの出し方」も、そして「わかっている」ということの意味も、根本的にちがうのです。
AIは間違えることもある
AIはとても便利な道具ですが、ときどき間違える(利用者が想定した回答を作れない)ことがあります。
それは、AIが学んでいるデータの中に、人間が昔つくった「かたより」や「古い考え方」が含まれていることがあるからです。
たとえば、昔の写真や文章ばかりで学んだAIは、「科学者といえば男性」「看護師といえば女性」など、今は変わりつつある考え方を、そのまま受け継いでしまうことがあります。
しかも、AIが何層も重ねた計算の中でどんな特徴を使っているのか、人間が完全に理解することはとても難しい場合があります。
だから、「AIが言っているから正しい!」と信じすぎず、「どうしてこの答えが出たんだろう?」「どんなデータから学んだのかな?」と考えることも大切です。
身近な例はちょっとだけ
私たちの生活の中にもAIはたくさん使われていますが、社会でどんなふうに使われているかは次回くわしくお話しするので、今回はほんの少しだけ。
たとえば、翻訳アプリや音声アシスタント(「明日の天気は?」と聞くと教えてくれるもの)、動画サイトのおすすめ機能などがあります。
これらはたくさんの言葉や行動データを学んで、「たぶんこれがいちばんよさそう」と答えを出してくれています。
おわりに:ふしぎに思う心を大切に
AIのしくみを知ることで、私たちはAIともっと上手につきあえるようになります。
大事なのは、「どうしてこうなったんだろう?」「これって正しいのかな?」と立ち止まって考え、友だちや先生、家族と話し合うことです。
次回は、「AIってどんなふうに社会で使われているの?」をいっしょに見ていきます。
どんな場所で活やくしているのか、ぜひ楽しみにしていてくださいね。
|
もっと知りたい人におすすめ! 『AIの時代を生きる:未来をデザインする創造力と共感力』(岩波ジュニア新書) 『AIの世界へようこそ:未来を変えるあなたへ』(Gakken) |