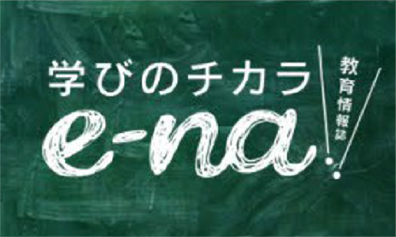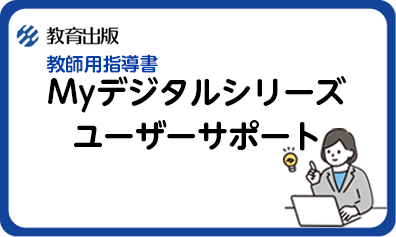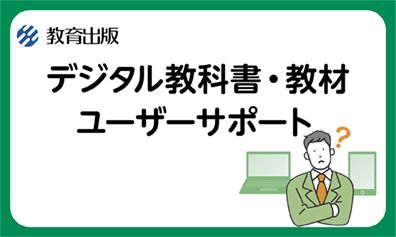もう一度古典を読もう
コラム 五月晴れは梅雨の晴れ間
● このページは,画面の幅が1024px以上の,パソコン・タブレット等のデバイスに最適化して作成しています。スマートフォン等ではご覧いただきにくい場合がありますので,あらかじめご了承ください。
日本では、明治5年(1872)まで、月が地球のまわりを一周する時間をもとに作られた太陰暦が用いられていました。ただし、太陽の運行も計算に入れて、閏月を設けていましたから、「太陰太陽暦」とも呼ばれます。
「立春」や「春分」「大寒」などの二十四節気は太陽暦によっています。『古今和歌集』に「年のうちに春は来にけりひととせをこぞとやいはむことしとやいはむ 在原元方」(巻一 春上)という歌がありますが、これは閏月の関係で立春が旧年中に来たことを歌ったものです。
月の満ち欠けは、古代の人の日々の生活に密接に結びついています。月の満ち欠けをもとにした太陰暦では、何月であっても、十五日の月はいつも満月でした。
四季は、一月から三月を春、四月から六月を夏、七月から九月を秋、十月から十二月を冬とし、それぞれ、「初・仲・晩(孟・仲・季)」に分けられました。
したがって、「初春」とは一月のことであり、今、年賀状に「初春」などと書くのはその名残です。また、「中秋の名月」(「仲秋」ではないことに注意)とは、秋のまん中にあたる八月の十五夜のことでした。
それぞれの月には、「
芭蕉が『奥の細道』の旅の途中、最上川で詠んだ
五月雨をあつめて早し最上川
の句の「