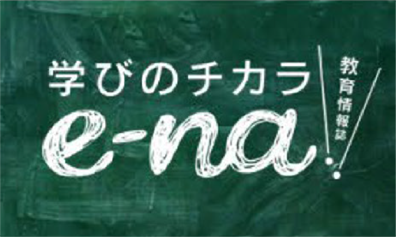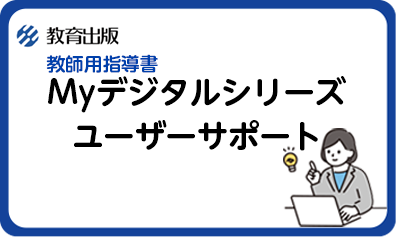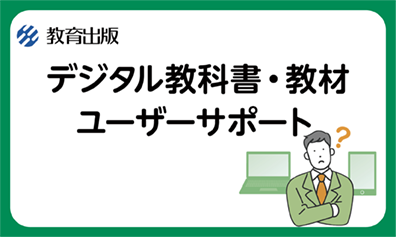Q2 東大寺の大仏の創建当時の規模は?
● このページは,画面の幅が1024px以上の,パソコン・タブレット等のデバイスに最適化して作成しています。スマートフォン等ではご覧いただきにくい場合がありますので,あらかじめご了承ください。
● ダウンロードに際しましては,あらかじめ免責事項をご確認ください。

東大寺の大仏
東大寺の大仏(盧舎那仏像)は,聖武天皇の命によって着工され,752年(天平勝宝4年)に開眼供養会が行われました。それ以来1200年以上にもわたって,維持され続けてきたのです。
まず,現在の大仏の大きさですが,これは,1974年(昭和49年)の大修復の際に,写真実測という方法で計られた数値が出ています。
では,昔の大仏は,今の大きさとは違っていたのでしょうか。
天平時代に造られてから今日にいたるまで,東大寺の大仏は何度か損傷を受け,その度に修補されてきました。大きな損傷には,下のようなものがありました。
786年(延暦5年)
尻の部分が破損
855年(斉衡2年)
地震のため頭部が落下
1180年(治承4年)
平重衡の兵火で頭部や手が損傷
1567年(永禄10年)
松永久秀の兵火で大仏殿が焼失,大きな損傷
修補が繰り返されてきたため,現在の大仏の中で,造られた天平時代当時のままの形を残している部分は,左大腿部褶襞の一部と台座の蓮弁部のみで,ほかは後世に修補されたものです。現在の大仏の大部分は,1567年に損傷を受けた後,江戸時代に入ってから修補した時のものということになります。
では,造られた当初の大きさは,どのようにしてわかるのでしょう。当時の大仏の大きさは,平安時代に書かれた東大寺の寺誌『東大寺要録』の中の『大仏殿碑文』という資料に記録されています。この資料では,当時使われていた「尺」という単位で記録されていますが,これをメートル法に換算することで,造られた当時の大仏の大きさを知ることができます。こうして算出した創建当時の大仏の大きさと,現在の大きさを比較してみましょう。
「尺」を用いた度量衡法である「尺貫法」で表された長さを,メートル法に換算する時には,通常,1891年に制定された度量衡法で定められた換算比率を用います(1尺=約30.303cm)。
ところが,この「尺」の長さは時代によって差があるため,原資料がつくられた時期に応じて,上の換算比率を修正して算出することになります。天平時代に用いられていた「尺」は「唐尺(天平尺)」とよばれており,唐尺の1尺は通 常の1尺の約9寸72分に相当します。上の表の数字は,当時の記録を,唐尺の換算比率でメートル法に直したものです。
このように比較してみると,現在見ることができる大仏は,最初に造られた時より全体の大きさは,若干小さくなっていることがわかりますが,顔の造作などは,むしろ大きくなっています。あおぎ見ることを意識したのでしょうか。
ところで,東大寺の大仏殿は,1180年と1567年の2度にわたって焼失しています。1回目の焼失の後,1195年に再建された時は,創建時の大仏殿とほぼ同じ大きさに造られました。
ところが,2回目の焼失の後,1709年に完成した大仏殿は,正面は約57mで,創建当時の約88mと比較するとかなり小さくなっているのです。現在の大仏殿は,世界最大の木造建築物として知られていますが,今から1200年前に建てられた大仏殿は,それよりさらに大きかったのです。
| 天平時代の大仏 | 現在の大仏 | |
| 座高 | 1580cm | 1498cm |
| 顔の幅 | 280cm | 320cm |
| 目の長さ | 115cm | 102cm |
| 耳の長さ | 251cm | 254cm |
| 鼻の高さ | 47cm | 50cm |
| 口の長さ | 109cm | 133cm |
| 掌の長さ | 313cm | 256cm |