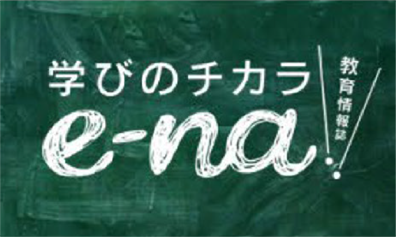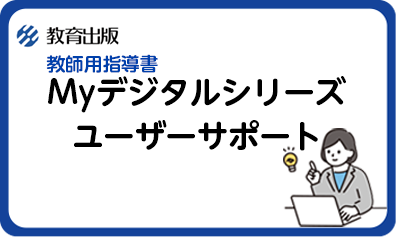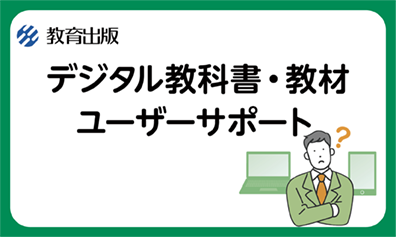Q3 田下駄 はどのように使っていたの?
● このページは,画面の幅が1024px以上の,パソコン・タブレット等のデバイスに最適化して作成しています。スマートフォン等ではご覧いただきにくい場合がありますので,あらかじめご了承ください。
● ダウンロードに際しましては,あらかじめ免責事項をご確認ください。

田下駄
田下駄とは,湿地や深田で作業する時に,作業能率を高めたり,足を保護したりするために使われた履物の総称です。農業の機械化が進むにつれて,今日では見られなくなりましたが,地域によっては20世紀に入ってからも用いられていた農具の一種です。
田下駄は,用途によって2種類に大別されます。田植えや草刈り,湿田での稲刈りなどの時に足が沈み込むのを防ぐために使用する「田下駄」と,田植え前の代踏みや肥料の踏み込みに使用する「大足」です。形は,枠型や箱型,かんじき型や足駄型など,さまざまな種類があります。各地の弥生時代の遺跡から出土している田下駄は,これらの原型と考えられています。
ところで,緒孔の数についてですが,弥生時代後期の代表的遺跡である登呂遺跡(静岡県)から出土した田下駄の足板を例に見てみましょう。登呂遺跡からは,緒孔が3つのものと,4つのものの両方が出土しています。
前者は板を縦長に,後者は板を横長に使い,足を中央にのせ,紐などで縛って固定したものと考えられています。長さ(幅)は40~50cmもあるので,これを両足につけて湿田の中を歩くのは,簡単ではなさそうです。
では,緒孔の数に違いがあるのはなぜなのでしょう。
弥生時代に田下駄が存在していたということは,当時の稲作で田植えが行われていたことを推測する重要な要素の一つになります。しかし,どのように使われたかは,まだ明確になっていません。
田植えや苗代作りに使われたのか,刈ってきた草を肥料として踏み込むような作業に使われたのか,はっきりした結論はまだ出ていないのです。したがって,田下駄の緒孔の数の違いについても,その使用方法が特定されていない現状では,用途別に作り分けられたものなのか,段階的に変化してきたものなのか,単なる形状の違いなのか,いずれもまだ推論の域を出ていません。